ふんわり いほこの引き出し「人生からダメ出しを消そう」を聞いて
2025年8月1日に放送されたラジオ番組 ふんわり いほこの引き出し「人生からダメ出しを消そう」を聞きました。

この「ふんわり いほこの引き出し『人生からダメ出しを消そう』」は、自己肯定感の育み方と、その阻害要因としての「ダメ出し」に焦点を当て、非常に具体的かつ実践的な視点で語られていました。
人間は、自分のテリトリーに入られると無意識に“あら探しモード”になる。
これは防衛本能とも言え、相手を攻撃しようというより、自己防衛的に相手のミスを見つけようとする反応です。
だから、ダメ出しをする傾向になるので注意しよう。
叱責や指摘が脳にどう作用するかが重要視されている。
とくに、「努力が報われなかった」という体験は、脳にダメージを残す。
これが積み重なると、自己肯定感の低下、やる気の減退、好奇心の喪失など、ネガティブな影響を生む。
「目論見どおり」に叱られるならば、子ども(あるいは大人)も納得できる。
たとえば、悪さをして叱られるのは予測範囲内であり、むしろ経験学習となる。
しかし、努力した結果が無視されたり、90点に対しての10点のミスばかりが指摘されるような状況では、「自分は何をやっても認められない」と感じてしまう。
まず、できている部分をしっかりほめよう。
推奨されるのは、誉め言葉や感謝からのダメ出しや、あるいは、何でもない話からのためだしである。
子どもも大人も、自分がどういう反応をされるかを予測して行動しています。
だから、予想外のダメ出しは心に深く刺さる。
「納得できる叱責」と「傷つくだけのダメ出し」は違うという視点は、教育にも職場にも通じる真理だと感じました。
「こっちはダメ」より「こっちにしてね」と言い換えることによって、望ましいイメージが脳に残る。
これは認知科学に基づいた有効なアプローチで、指示の仕方ひとつで行動が変わるという事実を示している。
否定ではなく、肯定の方向を示すという発想の転換が、心を育てる。
同様に、「飛び出しちゃダメ」は即時の危険回避として有効だが、日常的な場面では提案型が好ましい。
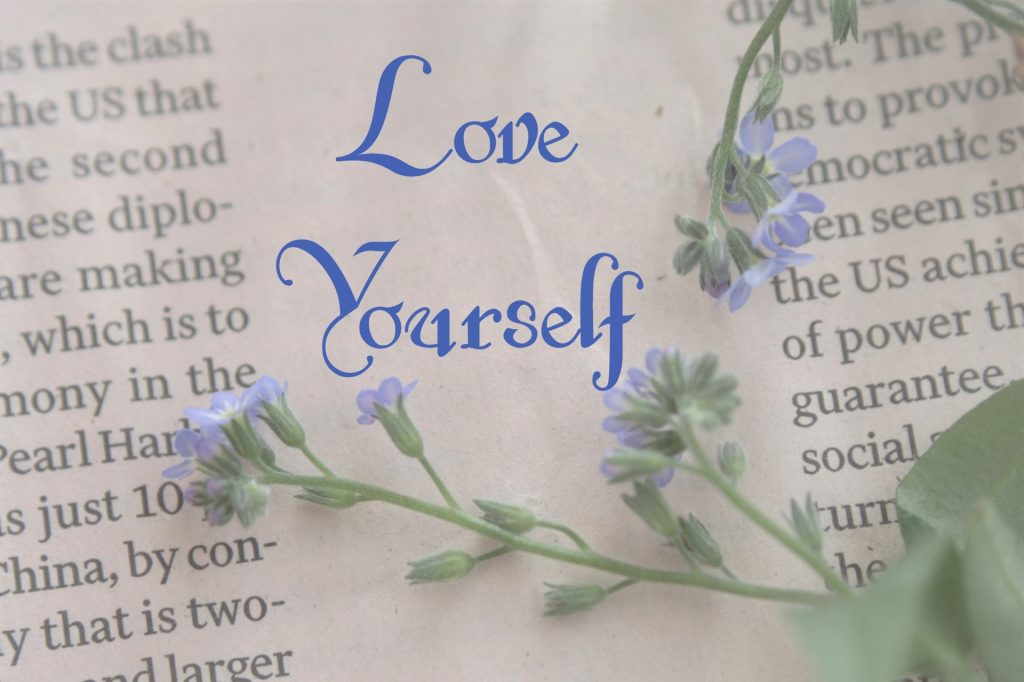
「これ結構ヤレる」という感覚、この万能感が、実は好奇心や集中力の源泉となっている。
とくにゲームなどの活動では、徐々に成果が出ることで万能感が高まる。
ゲームやお手伝いを通して「自分ってできる」という感覚を持てることが、自己肯定感につながる。
子どもが夢中になるものを頭ごなしに否定するのではなく、「なぜ夢中なのか?」を理解しようとする姿勢が求められると感じました。
「すみません」を「ありがとう」にかえるといい。
例えば、「気を付けます。ありがとうございます。」と言うと、相手の指摘がアドバイスになる。
脳も前向きになれる。
同じ状況でも、言葉の選び方で脳の反応が変わるというのは、実に示唆に富む指摘です。
実際には、日々の生活でイライラしたり注意したくなる場面は多くあります。
しかし、それに対して自分を責める必要はない。
人間は完全無欠ではないし、そうである必要もない。
「できる範囲でやさしく言い直す」ことが、心を育てる大きな一歩になるというメッセージが、心に残りました。
この番組は、「ダメ出し」を単なる口うるささや指導の問題としてではなく、脳科学・心理学・コミュニケーション論の観点から、多角的に捉え直している点が非常に印象的でした。
子育て中の親はもちろん、教育関係者、部下をもつビジネスパーソン、さらには自分自身への言葉のかけ方を見直したい人にも、強く響く内容です。
「人生からダメ出しを消そう」とは、決して甘やかすという意味ではなく、「人を育てる言葉を選び直そう」という優しさに満ちた提案だと受け取りました。
