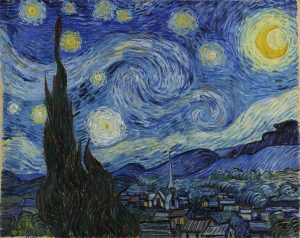マイあさ! 著者からの手紙 『あの人の調べ方 ときどき書棚探訪』を聞いて
2025年7月13日に放送されたラジオ番組 マイあさ! 著者からの手紙 『あの人の調べ方 ときどき書棚探訪』を聞きました。

番組では、作家・研究者・漫画家・編集者・翻訳家といったさまざまな知的職業人が登場し、それぞれの「調べ方」が紹介されました。
彼らの方法は一様ではなく、アナログとデジタルの両方を柔軟に使い分ける姿勢が印象的です。
紙の本を重視する人は、本棚を眺める「ブラウジング」から得られる偶然性や、書き込みから読み取る「前の持ち主の思考」に価値を見出しています。
私が特に印象に残ったのは、「紙の書き込みを見て前の持ち主の思考をたどる」というエピソードです。
これは、知識を受け取るだけでなく、誰かの知的営みに触れるという、人間的で感性的な体験です。
情報の断片を「つなぎ合わせる」過程で、人は歴史とつながり、他者の思考と出会い、そこから新しい視点を得ているのだと感じました。
デジタルを活用する人は、ネットの便利さを認めつつ、情報の信頼性を見極める「批判的読解力」が不可欠だと語ります。
図書館派は、分類された書架を歩くことで未知の本と出会う「偶然性」を重視。
整理を重視する編集者は、情報は集めるだけでなく「整理と活用」があって初めて意味を持つと説き、紙・デジタル双方でのアーカイブ術を紹介しています。
現代は情報過多の時代ですが、それを「どう扱うか」が個人の知性を決定づける。
調べる力とは、情報に対する姿勢であり、生き方そのものを反映しているようにも思えます。
単純な二項対立(紙 vs デジタル)ではなく、それぞれの長所と短所を認めた上で補完し合う姿勢が共通していました。
紙の長所は、「感覚的な操作性」や「偶然の出会い」であり、デジタルは「迅速さ」や「検索性」です。
特に、「今はもうない店の雰囲気を紹介するブログが消えている」という指摘は、デジタル情報の脆弱性と、紙による保存の意義を強調するものでした。
最後に強調されたのは、「テーマに沿った調べ方」以上に、「情熱」が何よりも重要だということです。
どんな手段を使うにせよ、探求の根底にあるのは知的好奇心と執念。この点において、すべての登場人物が共通しています。