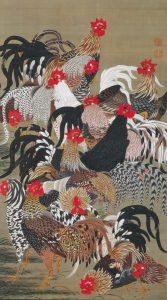《知っているようで知らない「自律神経」の話》小林弘幸(自律神経研究者) ラジオ番組 まんまる ひとのわ(NHK) を聞いて
2025年7月10日に放送されたラジオ番組 まんまる ひとのわ 知っているようで知らない「自律神経」小林弘幸(自律神経研究者) の話を聞きました。

夜勤の人への提案として「朝食をとる」「起きる時間と寝る時間を一定にする」「入浴する」といった具体的なリズム作りが挙げられています。
自律神経は交感神経(活動)と副交感神経(休息)のバランスで成り立っており、乱れると心身の不調に直結します。
夜勤でリズムが崩れやすい人ほど「規則性」が重要であることが分かります。
「片付け」は単なる家事ではなく、脳や心の整理にもつながるとされています。
視界に入る情報が整うことで、選択の迷いが減り、精神的負担が軽減される。
この考えは心理学でも支持されており、視覚的な秩序が自律神経に好影響を与えると考えられます。
「階段を使う」「動くこと自体が血液循環を促す」という話は、軽い運動習慣が自律神経を整えるという科学的な視点と一致しています。
特に「血液が下に溜まりやすい」という生理的な現象への具体的な対処法が、身近で実践しやすい形で語られていたのが効果的です。
「3行日記」(よいこと、悪いこと、明日の予定を書く)というのはハードルが低く、継続しやすい工夫です。
ポイントは「手書き」で行うという点。手を動かすことが脳への刺激になり、結果的に気持ちの整理や前向きな感情につながるという心理的効果もあります。
一対二の呼吸(吸う:吐く=1:2)(例えば、3秒吸って、6秒はく)は、副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらすとされる方法です.
「わくわく」すれば、「幸せホルモン(オキシトシン・セロトニン)」がげて、いいというのも納得です。
これらから、感情と身体のつながりが非常に重視されていることがうかがえます。

この番組は、「自律神経」という一見専門的なテーマを、驚くほど身近でやさしいアドバイスにまで落とし込んでいるのが魅力です。
「片付けをする」「階段をのぼる」「日記をつける」「呼吸を整える」といった、一つひとつは地味に見える行動が、実は心身のバランスにとても大きな意味を持っているという気づきが得られました。
とくに印象に残ったのは、「まず片付けてから休む」という考え方です。多くの人は「疲れたからすぐに横になる」ことでリラックスしようとしますが、かえって自律神経が興奮したままで休めないという指摘にはハッとさせられました。
また、「3日坊主でもいい」という言葉には、完璧を求めず、柔らかく続けることの大切さが込められていて、励まされました。
この放送は、心と体のバランスに悩む多くの人にとって、優しく背中を押してくれる内容だったと感じます。