NHKスペシャル「不透明な米中対立 日本の活路は」を見て
2025年5月18日に放送されたNHKスペシャル「不透明な米中対立 日本の活路は」を見ました。

この番組は、日本の未来に対する一種の“危機と希望”の両面を提示しています。
米中対立は単なる貿易問題ではなく、経済秩序の再編という地殻変動に等しいものであり、日本はそれに巻き込まれるだけでなく、能動的に戦略を立て直す好機にもなっています。
特に印象的だったのは、「選択と分散」という視点です。
これは、グローバル資本主義における“集中と効率”の時代が終わりを迎え、多様性と柔軟性を備えた“しなやかな強さ”が求められる脱グローバル化の新時代の到来を意味します。
複数の地域や領域にリスクヘッジする経営が必要。
加えて、経営者に「ファンドマネージャー的発想」が求められるという指摘は、企業単体ではなく“国家規模の経営感覚”が要る時代ということを示唆しているでしょう。
したがって、中国や米国だけでなくインド・インドネシアなどの新興国と連携する動きがさらに広がると予想されます。
また、米中対立により、半導体工場やデータセンターが日本に回帰しつつある。
台湾は、アメリカとは対立的な構造の中で圧力を受けて投資が進んでいますが、日本とは信頼と利益を共有する関係の中で投資が進んでいるという指摘は重要です。
投資の一極集中が変わり、日本の相対的価値が再評価されていることを理解して行動することが必要です。
過去には“自由競争”で淘汰されていた企業に、再び雇用と事業機会が戻りつつある。
この点も、単なる回復ではなく、戦略的な選択の結果としての“地政学的リターン”といえるでしょう。
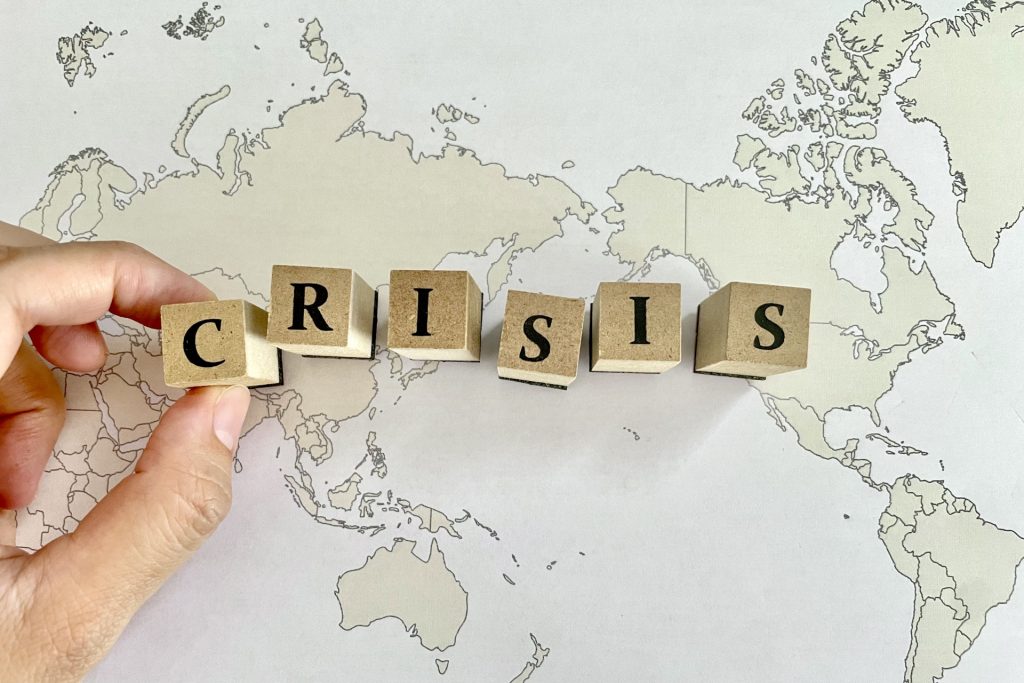
ただし、この変化は必ずしも全員にとってプラスとは限りません。
高賃金を支払えない企業は淘汰され、変化に乗り遅れた者は取り残される。
だからこそ、「いま下す判断が、10年後・15年後の日本の姿を大きく左右する」という言葉には、未来を見据えた真剣な警告と、必要な改革をやり遂げる強い決意の必要性が込められていると感じました。
この番組は、米中の対立という出来事を通じて、世界経済の大きな変化や、日本が直面している選択の難しさ、そしてこれから進むべき方向について、深く掘り下げていました。
信頼と利益を共有する関係を重視してきた日本の立場こそが、これからの不安定な時代を生き抜くための新しい戦略として見直されているように感じます。
これからの日本には、これまでと同じやり方を続けるのではなく、国際情勢をしっかりと見極めて、必要ならば発想を大きく変えることがますます必要になってくるでしょう。

