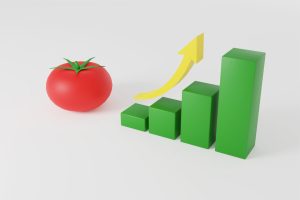ラジオ番組 ふんわり「タテ型回路VSヨコ型回路、脳の中には二つの答えがある」を聞いて(2)
2025年4月11日に放送されたラジオ番組 いほこの引き出し「タテ型回路vsヨコ型回路、脳の中には二つの答えがある」(放送局:NHK)を聞きました。(その2)
① この番組で、まず心に残ったのは、「人が成熟していくっていうのは、ハイブリッドになっていくこと」という一文です。
この一言には、人生のあらゆる場面で求められる変化への柔軟さと、それを通じて人が成長できるという希望が込められています。
タテ型の人がカウンセラーの勉強を通してヨコ型の回路を身につけたというエピソードも非常にリアルで、人は変われるし、意図的な学びと実践で思考の幅を広げられるというメッセージが力強く伝わってきます。
特に印象的なのは、「後天的に手に入れたものの方がプロフェッショナルとしては使いやすい」という視点です。
これは実感として非常に共感できます。
苦労して身につけたものこそ、意識的に使いこなすことができ、相手や状況に応じた「選択」ができるようになる。
それがまさに、真のコミュニケーション能力であり、「達人」と呼ばれる人の共通点なのだと思います。
時代の変化が速く、多様性が求められる今の社会において、最も必要とされるのはこのような柔軟で自在な“ハイブリッド型”の人間性かもしれません。

② この番組にあるように、職場での「急な残業依頼」ほど、頭の中で複雑な感情や思考が一瞬にして交錯する場面はありません。
特に「ヨコ型を起動しちゃうと、事情とか心情とか過去の履歴が1/1000秒で浮か」び、いろいろ愚痴がでる。
まさにその通りだと笑ってしまうほどの説得力があります。
そして、それが“人間らしさ”だという前提に立っているところが、この番組の優しさだと思います。
一方で、タテ型回路を起動すれば、「できる範囲でやります」という目的と条件の調整をすばやく行う冷静さが発動する。
これはまさに、状況に応じて“切り替えられる”人がプロフェッショナルである、という実践的なメッセージにつながっています。
③ この番組にある「ヨコ型は感情とともにタイムトラベルできる」という表現には、人間の脳がいかに感情と思い出を結びつけて記憶を取り出すかというメカニズムが、わかりやすく美しく描かれています。
これは冷静な分析というよりも、感性に訴えかける認知の魔法のようにうまく表現されています。
「なぜ素晴らしいかっていったら、人工知能にできないから。」という一文には、読者としてハッとさせられます。
AIには高速で正確な演算ができますが、人間のように“心配”という感情をトリガーにして30年前の出来事を思い出すことはできない。
それは、単なる情報処理ではなく、「生きてきた時間」の重みそのものだからです。

④ 相手が人の悪口を言う場合はどうすればいいのでしょうか。
共感もできないし、解決策を提案するのも違う気がして、いつも困ります。
「ひどいと思わない?」「そうね」って言っちゃうと、後で「○○さんもそう言ってた」となってしまう、というくだりは、まさにママ友関係や職場の人間関係でありがちな罠です。
共感が人間関係を円滑にする一方で、不用意な共感は“共犯”のように使われてしまう危険もあるという鋭い指摘に、ハッとさせられます。
そして、解決策としての「そっか、そうなんだね。」というフレーズは絶妙です。
感情には寄り添いつつ、是非の判断には踏み込まないという、共感と中立の絶妙なバランスを取った魔法の一言だと感じました。
これは、無理に正義を示さず、相手を否定も肯定もしない大人の知恵であり、まさに人間関係のサバイバル術とも言える巧みな表現です。