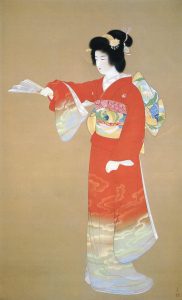マイあさ Biz「Z世代はAIをどう使っているか」を聞いて
2025年5月1日に放送されたラジオ番組 マイあさ Biz「Z世代はAIをどう使っているか」(放送局:NHK)を聞きました。
この番組は、Z世代(おおよそ15歳から24歳)がAI技術をどのように日常生活に取り入れているか、またそれに対する姿勢や価値観を多角的に描いた非常に興味深い内容です。
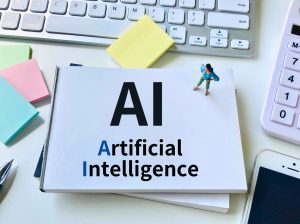
まず、Z世代がAIをエンターテイメントや自己表現の手段として活用している様子が描かれています。
特に、自撮り画像をAIで加工し、絵画風・韓国風などに変換してSNSのアイコンに使うといった行動は、彼らがAIを「創造的な遊び道具」として受け入れていることを示しています。
これは、技術の最先端に触れることが特別なことではなく、「当たり前の日常」になっていることです。
次に、Z世代がAIチャットを勉強の支援に用いている実態が語られます。
「レポートをAIに丸投げする」という懸念に対し、「先生のように使う」という姿勢があるという記述は、非常に希望を感じる部分です。
特に数式を入力して解説を依頼するといった利用は、AIを相手に能動的に問いかけ、自分の理解を深める手段として活用しているように見えます。
AIが出す情報の正確性を判断する情報リテラシーの必要性についても触れられており、これはまさに現代教育の大きな課題だと再確認しました。
受け身ではなく、「AIを活かしながら使いこなす」スキルが求められているのです。

また、Z世代がAIに悩み相談をしたり、上司との会話のシミュレーションに使ったりしているとのこと。
これは従来、友人や家族、あるいはカウンセラーが担ってきた役割を、AIが一部引き受けていることを意味しており、非常に象徴的です。
AIと話すことで「想定外を減らし、不安を和らげる」という使い方は、コミュニケーションに対する不安が強い若者にとって、AIが新たなメンタルサポーターになりつつあるという印象を受けました。
実際の社会ではミスや失敗が許されない空気もある中で、安心して準備ができる「練習相手」としてのAIの役割は今後ますます重要になるのではないかと思います。
そして、AIに変わられない能力を身につけたいとするZ世代の意識が明かされます。
AIを楽しみ・活用しながらも、「危機感」も持ち合わせているという、非常にバランスのとれた態度です。
技術への単純な肯定ではなく、自己の役割を見つめ直そうとする姿勢に、強い主体性と未来志向を感じました。
「AIに奪われる」ではなく、「AIに負けない・共存できるスキルを磨く」という前向きな意識が、Z世代が育っている環境の豊かさ、あるいは情報感度の高さを物語っているようです。
この番組は、Z世代のAIに対する多面的な関わり方――遊び・学び・相談・仕事・危機感――を見事に捉えている好例です。
AIというと専門的で堅いイメージがありますが、Z世代の手にかかるとそれは自然な生活の一部となり、「道具」として活かされているのがよく分かります。
今後重要なのは、こうした世代の感覚を理解し、彼らのAIリテラシーをさらに育てる教育や環境づくりだと思います。