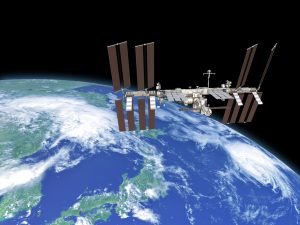「地方女性たちのイマ」上野千鶴子(東京大学名誉教授) ラジオ番組「マイあさ!」サタデーエッセー (NHK) を聞いて
2025年11月15日に放送されたラジオ番組「マイあさ!」サタデーエッセー「地方女性たちのイマ」上野千鶴子(東京大学名誉教授)を聞きました。

1.「地方女子の移動」を“個人の選択”ではなく“構造的必然”として描く視点
上野氏は、地方女性が都市へ移動する現象を、単なる「都会への憧れ」や「個人的事情」として扱わず、構造的なジェンダー格差と地方の労働・文化資源の不足から説明しています。
・北陸で女性流出が男性の2.3倍
・地元にやりたい仕事がない/低賃金で生活が厳しい
・地域社会からの結婚・出産の圧力
・行事や祭礼で女性が「裏方労働」を強いられる文化
これらは、地方社会の中に女性が主体的に“そこに生きる”ことを難しくする構造が積み重なっていることを示唆します。
この分析は、単なる現象の描写を超え、地方における「性別役割の固定化」のしぶとさを見抜く社会学的洞察に満ちています。
2.「残る女性」「戻る女性」「やって来た女性」という三タイプの提示
上野氏は地方にとどまる女性を大きく3パターンに分類し、いずれも単純化せず、背景の複雑さを包括的に示しています。
(1) とどまった女(選択肢がなかった)
・都会へ出たいが出られなかった
・実家との関係に左右される
→ 個人の意思ではなく、構造的な制約が強いケース。
(2) 戻ってきた女(故郷を選び直す)
・都会で“住む場所ではない”と感じた
・困った時に帰る場所として実家がある
・自分で選んで戻ったため、満足度が高い
(3) やってきた女(都会育ちの高学歴層)
・富山へ誘われて移住
・新しい環境で能力を発揮
・パートナーとの出会いも含め、主体的な選択
この三者の比較は、地方移住・定着をめぐる議論を「流出か残留か」という単純な構図から救い、人生選択の多様性と主体性のあり方を浮き彫りにしています。
3. 故郷への“愛着”と“離脱”の二重構造への洞察
上野氏は地方女子の多くが故郷の自然や風土、人間関係を強く愛していることも指摘します。
だからこそ、そこから離れる決断は「好きだから離れたくない」という感情との対立をはらみ、痛みを伴う選択になります。
・故郷の魅力:自然・食べ物・言葉・友だち・親族
・それでも外に出る:生活できる仕事、ジェンダー圧力の回避、新しい人生の創造
ここには、情緒的価値と経済的・社会的現実の相克が描かれています。
単なる「都会に行きたい」ではなく、「故郷を愛しつつも離れざるを得ない」という複雑な心情を丁寧に描く点に、語りの深みがあります。

4. 人生の満足度は“選択肢の大きさ”に比例するという核心
最後に示される「選択肢の大きさが人生を決める」という主張は、地方女性だけでなく現代を生きるすべての人に通じる普遍的なメッセージです。
地方に生まれること自体が選択肢の数を制限してしまう構造的な問題である一方で、
・“出られない”という制約
・“戻る”という選択
・“やって来る”という外部からの参入
など、人生の可能性をどれだけ自分の手で開けるか——その差が満足度に結びつくことは、都市・地方を問わない重要な指摘です。
5. 感想
地方の人口流出を「地域の話」で終わらせず、女性の生きづらさ=地域構造+ジェンダー規範の相互作用として説明している点は、上野氏らしい鋭さです。
3タイプの女性像を示すことで、地方女性の人生が「成功/失敗」「残留/流出」といった単純な分類では語れないことを明確にしています。
どの生き方にも尊厳を認める語りが印象的です。
多くの社会論が見落とす“感情”の領域まで視野に入れ、地方女性が背負う心情のリアリティを浮かび上がらせています。
これにより、聴き手は地方の課題を「データ」ではなく「人間の物語」として受け取れます。
戻ってきた女性・やって来た女性の満足度の高さは、「主体的に選んだ人生は強い」という普遍的なメッセージを感じさせました。