「金融政策を左右する『基調的なインフレ率』」渡辺努(経済データ解析会社創業者・東京大学名誉教授) ラジオ番組「マイあさ!」マイ!Biz・経済展望を聞いて
2025年11月7日に放送されたラジオ番組「マイあさ!」マイ!Biz・経済展望「金融政策を左右する『基調的なインフレ率』」渡辺努(経済データ解析会社創業者・東京大学名誉教授)を聞きました。

1.基調的なインフレ率とは何か
渡辺氏は、金融政策の鍵となる「基調的なインフレ率」について、次のように解説しています。
単なる消費者物価指数(CPI)とは異なり、一時的・極端な価格変動を除外して計算される。
600品目ある物価データから、外れ値(例:異常に高騰した米や食品など)を除外して「実勢に近い平均的な物価動向」を見る指標。
これは「経済の本質的なインフレ圧力を見極める」ために有効な指標ですが、消費者の体感とは乖離しやすい側面を持ちます。
2. 消費者感覚と日銀の視点のズレ
番組では、基調的インフレに対する消費者の違和感が指摘されます。
消費者は、日々の買い物(特に食料品)でインフレを強く感じる。
しかし、基調的インフレでは食品の一時的高騰は除外されるため、「日銀は実態を見ていない」と映る可能性がある。
例として挙げられたのが、「米価の高騰」。これが基調に含まれないことで、家計の実感とのギャップが拡大します。
3. 利上げの判断を左右する“春闘”と“賃金”
渡辺氏は、現在の日銀の姿勢が「慎重な利上げ見送り」である理由を、次のように整理しています。
来年の春闘での賃上げがカギ。
トランプ政権による対中関税(再強化)も物価に影響し、来春の賃金動向次第で、「インフレが定着するか否か」が見えてくる。
仮に食品が上がっても、賃金がそれを上回るペースで上がれば問題はない。
この論点は、「一時的な価格上昇」と「賃金主導の持続的インフレ」の違いを明確にし、日銀が賃金動向を重視する理由に説得力を持たせています。
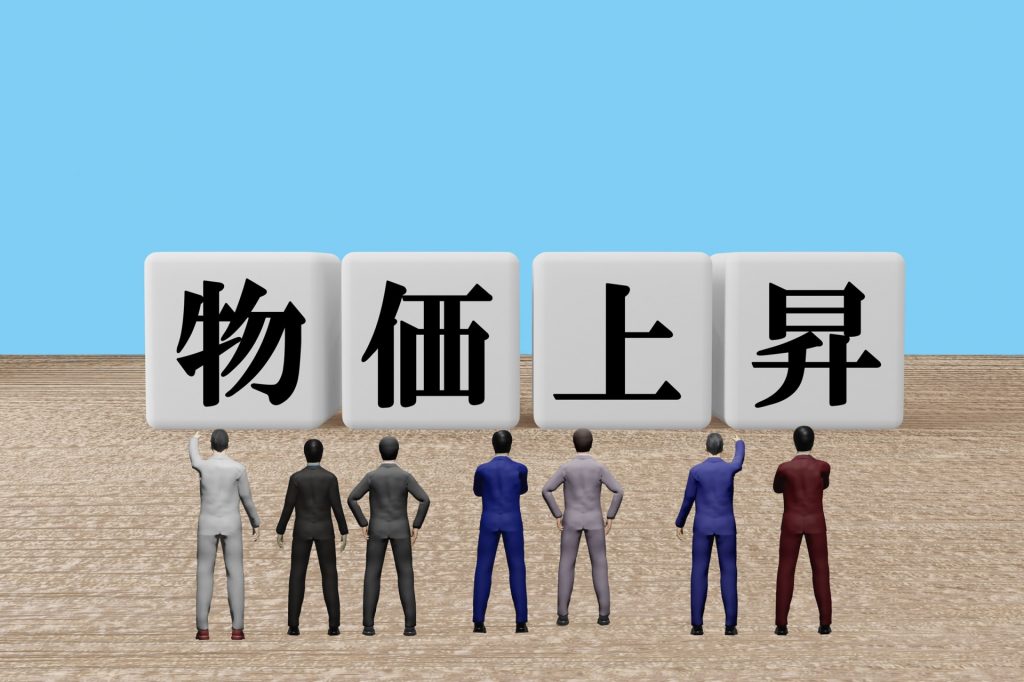
4. 感想
渡辺氏の解説は、金融政策の舞台裏を非常に丁寧かつ実務的に可視化した点において、たいへん高く評価できます。特に以下の三点が秀逸です。
①経済モデルと生活実感の「ズレ」を誠実に提示
「米が高いのに、日銀は利上げをしない」という疑問に対し、統計処理上のロジックと政策的背景を丁寧に説明しており、視聴者の疑念を知的に解きほぐします。
②一般リスナーにも伝わるような例示
「米」「家賃」「春闘」など、日常に密着した具体例を使うことで、マクロ経済の難解な概念を平易に解説しています。これは、公共放送での専門家解説として理想的なアプローチです。
③今後の政策運営の難しさを冷静に指摘
「基調的インフレ率」という合理的な概念が、複雑な現実の前では機能不全に陥りかけているという視点は、新たな問題提起であり、日銀の枠組みを今後どう進化させるべきかを考える糸口になります。

