「日本の技術がフィジーの天気予報に貢献!」 黒岩宏司 (JICA専門家) ちきゅうラジオ(NHK) を聞いて
2025年9月14日に放送されたラジオ番組 ちきゅうラジオ 「日本の技術がフィジーの天気予報に貢献!」黒岩宏司 (JICA専門家)を聞きました。
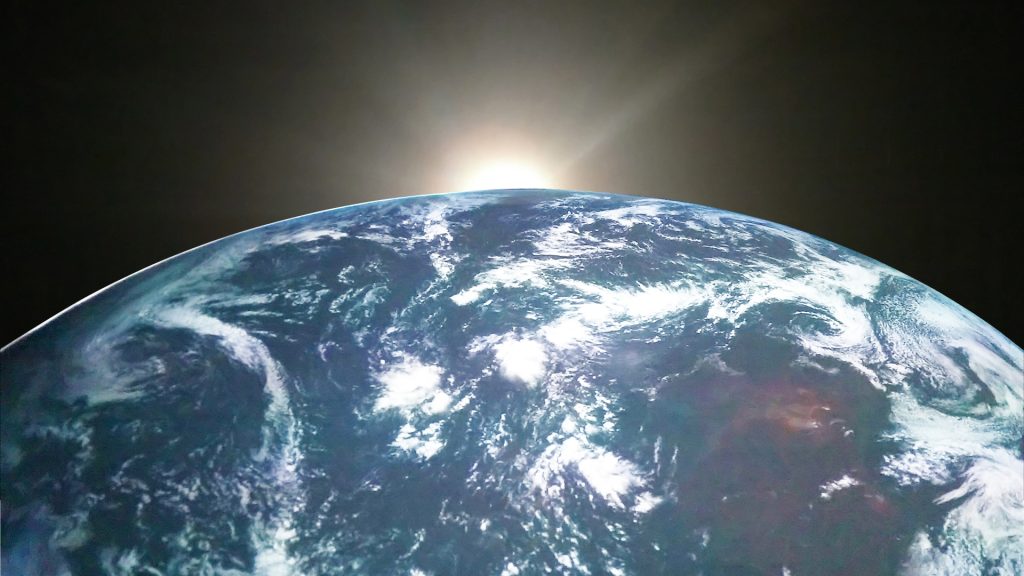
1.地理的連携と気象安全保障
この番組では、フィジーという一見日本と無関係に思える国が、実は「日本の気象安全保障に深く関係している」ことを明らかにしています。
南太平洋のサイクロンなどの異常気象が、偏西風や海流を通じて日本の天候にまで影響を与えるという視点は非常に重要で、気象観測のグローバルな連携の必要性を強く印象づけます。
2. 「ひまわり」衛星の役割と有用性
気象衛星「ひまわり」が、赤道上空という地理的利点を活かし、南太平洋から日本までを常に観測しているという点も明快に解説されていました。
「雲画像からサイクロンの位置・強度・動きを推定できる」という記述は、静止衛星の利点と、遠隔観測のリアルタイム性を理解するうえで非常に有益です。
3. 技術支援の内容:ハードとヒューマンの両輪
日本の支援が、単に「装置を渡す」だけでなく、観測機器の使い方の訓練や、気象予報士の人材育成にまで及んでいる点は特筆すべきです。
「気象の仕事は、時間とルールに厳密でなければならない」という言葉には、科学技術と倫理・規律の結びつきが見えます。
4. 観測データの「質」と「量」
全球予報モデルにおいて、観測データの「数」と「精度」が不可欠であるという点の説明も非常に重要です。
特に観測点が少ない南太平洋では、一つ一つの観測の正確性が、全球スケールでの天気予報の信頼性を左右するという視点は、多くのリスナーにとって新鮮だったのではないでしょうか。

5. 感想
この番組は、難解になりがちな「気象観測技術の国際協力」について、非常に噛み砕いた語り口で伝えており、技術情報と人間的ストーリーをバランスよく融合させる構成が光っていました。特に「観測器の使い方から人材育成まで」という広範な支援の全体像を、リスナーが実感をもって理解できるように配慮されていました。
フィジーという国を「支援されるだけの国」として描くのではなく、南太平洋の気象観測の中核を担うリーダー的存在として描写していた点も、非常にフェアで現代的な国際報道のあり方でした。これは、日本の役割を「教える者」から「共に学び、共に備える者」へとシフトさせていることを象徴しています。
フィジーという国名を聞いて、「ビーチリゾート」や「地理的に遠い南国」といったイメージしか持っていなかった人も、この放送を聞くことで「日本の天気を支える観測最前線の仲間」という新しい見方を得られたのではないでしょうか。
また、科学技術がただの「便利な道具」ではなく、命と生活を守るための知恵と協調の産物であることも、改めて感じさせてくれる内容でした。
「気象は、国境を超えて人類が協力すべき“地球の共通言語”である」——この放送は、それを見事に伝えてくれました。
気象という日常的でありながら、国際的なテーマを、わかりやすく、感情と知性の両面から伝えてくれた、非常に優れた番組だったと思います。

