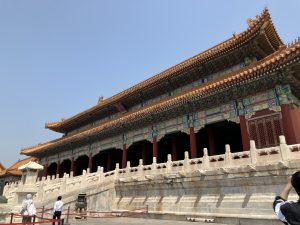「ミネルバ式 最先端リーダーシップ」黒川公晴 著 / 語り 荒木博行(武蔵野大学アントレプレナーシップ学部教授) ラジオ番組「マイあさ!」本を仕事にいかす(NHK) を聞いて
2025年10月23日に放送されたラジオ番組 「マイあさ!」「ミネルバ式 最先端リーダーシップ」黒川公晴 著 / 語り 荒木博行(武蔵野大学アントレプレナーシップ学部教授)を聞きました。

1.世界最先端の学びの実験場 ― ミネルバ大学の構造的革新
番組で紹介されたミネルバ大学は、従来の大学の枠組みを根本から変える実験的な教育機関です。
キャンパスを持たず、学生が世界8都市を巡りながら現地課題に取り組むという構成は、知識を「現場知」へと変換する装置のようなものです。
オンライン授業であっても、全員が顔を出し、発言を求められる「アクティブラーニング」を徹底する点で、“傍観者を作らない教育”を体現しています。
これは、従来の日本的教育文化(受動的・一方向型)への痛烈なアンチテーゼでもあります。
2. 適応型リーダーシップ ― 「正しさ」より「柔軟さ」
黒川氏が強調する「適応型リーダーシップ」とは、
「変化を見極め、それに合わせてリーダー自身の在り方を変える力」です。
これまでの「カリスマ型」「統率型」「成果主義型」リーダー像とは異なり、環境の流動性に対して“思考と姿勢を柔らかく保つことを要諦としています。
番組内で紹介された事例としては「リーダーが指示を減らし、問いかけに変えたら提案数が倍増した」ということ。
それは単なる手法の転換ではなく、リーダーの内的変容(コントロール思考から信頼思考へ)を象徴しています。
これは心理学的には「自己効力感の移譲」であり、組織行動論的にも「権限委譲」の実践例といえます。
3.「必殺技」からの脱却 ― 経験知を問い直す知的謙虚さ
黒川氏が最も鋭く指摘しているのは、「過去の成功体験が、今を阻む罠になる」という現代的パラドックスです。
“必殺技”にしがみつくリーダーは、変化に対応できず、部下の創造性を奪う。
これに対して必要なのは、「自分の正しさを疑う勇気」=知的謙虚さ(intellectual humility)です。
この概念は、近年のハーバード大学のリーダーシップ研究でも重視されており、黒川氏の主張が国際的理論潮流と合致していることを示しています。

4. 感想
黒川氏のリーダーシップ論は、哲学的でありながら極めて実践的です。
「正しさへの疑い」「知的謙虚さ」「面白がり力」といった概念は抽象的に見えますが、具体的な組織変革の場面に結びついて語られているため、聴き手は即座に自らの経験と重ね合わせることができます。
理論と現場を結ぶ“ミネルバ的教育の精神”が、著者自身の語りにも宿っているのです。
従来の日本企業に多かった「俺についてこい型」リーダー像を相対化し、“強さ”ではなく“しなやかさ”を重視しています。
「面白がる」という言葉をリーダーシップの核心に据える発想は、極めて新鮮です。
困難や変化を“脅威”ではなく“好奇心の対象”として見る視点こそ、現代社会の不確実性を生き抜くための知的態度です。
これは単なる精神論ではなく、好奇心が創造性を駆動する心理的メカニズムを踏まえた科学的提案でもあります。
この番組で描かれた『ミネルバ式 最先端リーダーシップ』は、リーダーシップを「テクニック」から「人間の在り方」へと昇華させた点で、特筆に値します。
「知的謙虚さ」「面白がり力」「正しさを疑う勇気」――これらは、単なるビジネススキルではなく、人が成熟していく過程で育まれる精神的成熟のリーダーシップです。
番組全体を通じて感じられるのは、「学ぶとは変わることである」「リーダーとは学び続ける人である」というメッセージ。
それは、教育・組織・人生のすべてに通底する、現代的ヒューマニズムの宣言でもあります。