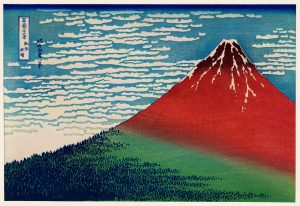「トランプ大統領 vs.FRB ”対立の深層」 小幡績(慶応大学大学院教授) ラジオ番組「マイあさ! 」(NHK) を聞いて
2025年8月29日に放送されたラジオ番組 マイあさ! マイBiz 「トランプ大統領 vs.FRB ”対立の深層」小幡績(慶応大学大学院教授)を聞きました。

1.トランプ大統領の金利引き下げ要求
トランプ大統領がFRBに対し、公然と金利引き下げを要求するという構図は、中央銀行の独立性に対する強烈な挑戦でもあります。
彼の目的は短期的な景気刺激と株価上昇による「政治的成果」の最大化であり、「選挙対策」としての金融政策介入という構図が見えます。
2. パウエル議長のスタンスと金融政策の独立性
これに対し、パウエル議長は「政治的圧力に屈しない」ことを重視し、インフレ抑制と金融の安定という長期的視点に立脚したスタンスを保ち続けている。
この態度こそが、中央銀行の独立性の象徴です。
3. 金利政策をめぐる欧米の温度差
番組で示されたように、欧州は金利を引き下げ始めているのに、アメリカは慎重姿勢を崩さない。
その背景には、インフレの再燃リスクと、住宅市場の過熱・減速という相反する経済指標の中で、どちらを優先するかという判断の分岐があります。
4. 「格差とインフレ」への視点の重要性
番組での最も注目すべき論点は、「インフレで最も困るのは低所得者層である」という点に踏み込んだ点です。
金利引き下げによって得をするのは主に資産を持つ人々です。
一方、インフレによる生活費上昇は、非資産層にとっては直接的な打撃となる。
この視点から見ると、FRBの慎重姿勢には社会的公正という文脈も隠れています。

5. 「景気とインフレの連動性の崩壊」という現代的課題
「景気が悪くてもインフレになる」「景気が良くてもインフレにならない」といった、過去のセオリーが通じない時代に入っていることを番組は鋭く指摘しました。
これは資産価格の過熱や富裕層の消費力の集中が引き起こす「分断経済」の表れであり、現代経済の不確実性を端的に表しています。
6. 感想
この放送は、単にトランプとFRBの対立という表層的なニュース報道にとどまらず、その背後にある制度的問題(中央銀行の独立性)、経済政策の功罪(金融緩和 vs. インフレ抑制)、そして社会的影響(格差・低所得者層の苦境)にまで切り込んでいます。
まさに「大人の教養」としての経済解説の模範と言える内容です。
解説者の小幡績氏(慶応大学大学院教授)は、短期と長期の視点、政治と経済のねじれ、政策の副作用などを、複眼的に捉えています。
「インフレは数字の問題ではなく、“誰が困るか”の問題である」といった視点は、単なる経済学ではなく倫理的・社会的洞察も含まれており、聴き応えがありました。
「今の経済はわかりにくい」「うまくいかないと腹が立つ」という庶民感情に正面から向き合い、それを「八つ当たりが専門家不信につながる」と分析する姿勢は、専門家と市民の断絶を乗り越えようとする誠実さを感じさせました。
このバランス感覚は、ポピュリズム的な経済論調とは一線を画すものです。
私たちがニュースの表面だけでなく、その裏にある構造や価値観の対立に目を向けることで、民主主義社会におけるより健全な議論が可能になる。
そう思わせてくれる、良質な報道であったと感じます。