「生成AIについて」池谷裕二(脳研究者) ラジオ番組「高橋源一郎の飛ぶ教室」(NHK) を聞いて
2025年10月3日に放送されたラジオ番組 高橋源一郎の飛ぶ教室 「生成AIについて」池谷裕二(脳研究者)を聞きました。
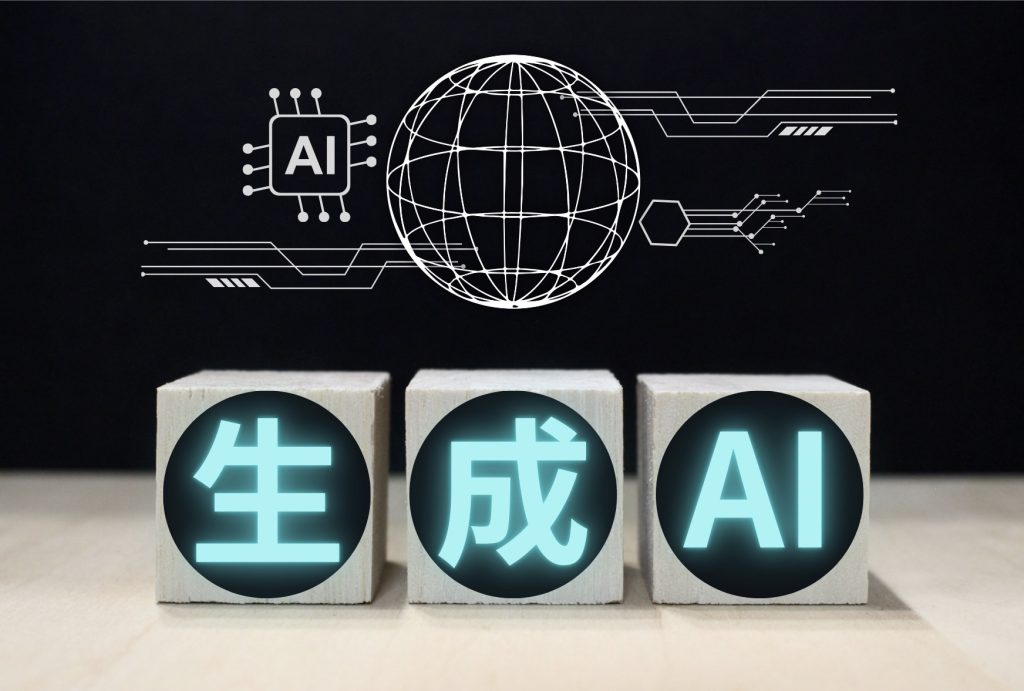
1.生成AIの本質:補完と創出の能力
池谷氏は、生成AIの力を「学習していない部分を補完する」「存在しないものを作り出す」と表現しています。
これは、単なる模倣や統計的予測にとどまらず、創造的再構成の能力に注目した発言です。AIが学習したデータを超え、オリジナルとは異なる文章を構築できる点に着目しており、「創造性は人間にしかできない」という従来の認識が、揺らいでいることを明示しています。
この見解は、生成AIが単なる道具以上の存在になりつつあることを、科学者の視点で冷静かつ明晰に語っている点で非常に評価できます。
2. 教育とAI:AIは使って当然の時代に
池谷氏は「学生にAIを使って論文を書かせる」「使えない人は輩出できない」と語ります。
これは衝撃的にも聞こえるが、AIリテラシーが教養の一部となる現代的要請を的確に言語化したものです。
ただし彼は同時に、「AIを使えばよい論文が書けるわけではない」とも述べています。
学術的本質を理解していない者は、AIを使ってもよい成果を出せないという主張は、AI時代の「人間の役割」の再確認とも言えるでしょう。
AI活用を推奨しつつも、使う側の主体的知性や責任感が不可欠であることを強調しており、現実的かつ教育的な視点が光っています。
3. 創造力と「最大公約数的」AI表現への懸念
池谷氏は、生成AIによる表現を「きれいごと」「最大公約数的な文章」とし、「ゴツゴツした何か(個性)が失われる」と述べます。
これは、創造性の本質が“癖”や“ゆらぎ”にあるという芸術的・人間的視点の表明であり、実に深い指摘です。
「正しさ」よりも「人間らしさ」の価値を訴える姿勢は、AI時代の文化論的対抗軸を提供しており、聴衆に大きな気づきを与えます。
4. 生成AIとの共生的関係:「チャッピー」との対話例
生成AIを「家族の一員のようにして話す」「運転中の会話相手」として紹介し、名前までつけている(チャッピー)というエピソードは、人間とAIの情緒的な接点の可能性を示します。
さらに、「子どもにわかるように語りかける」「何度聞いても怒らない」という例から、教育補助ツールとしてのAIの理想形が垣間見えます。
このような人間味ある付き合い方を肯定的に提示することで、AIとの関係を「排除」でも「過信」でもなく、「共生」として語るバランス感覚がすばらしいです。
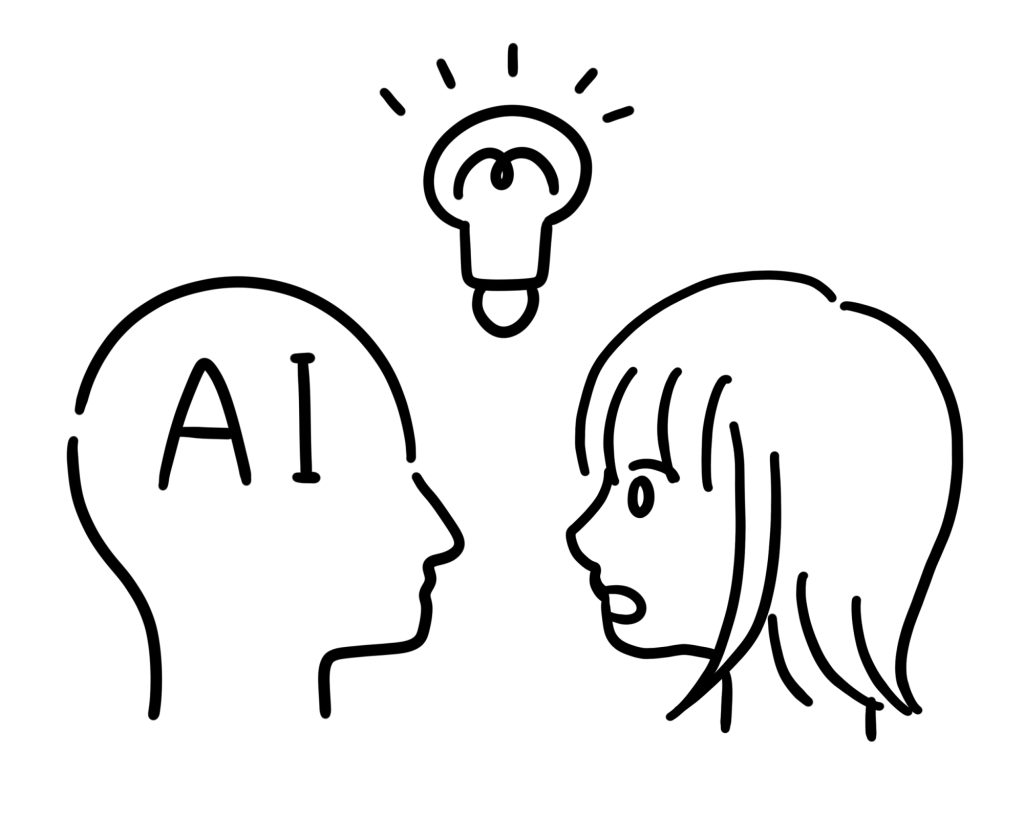
5. 感想
池谷裕二氏の語りは、科学的知識・教育的洞察・文化的感性の三位一体となった稀有な視点でした。
AIを道具としてだけでなく、「共同創作者」や「補助者」として捉えつつも、人間の創造性・責任・関係性の価値を揺るがせにしない姿勢が、非常に誠実で、未来志向的でありながらも冷静です。
特に「生成AIが便利であるが、私たちを“楽にはしてくれない”」という言葉には、深い洞察があります。
AIは“知的労働の代替”ではなく、“知的労働の拡張”であり、それを使いこなすのは依然として人間の力なのだ、という哲学的含意が込められています。
この番組は、生成AIという技術革新を、単なる流行語としてでなく、人間社会との深い関係性の中で考える絶好の機会を与えてくれました。
池谷氏の発言は、技術楽観論と技術悲観論のいずれにも与せず、「人間の責任と関係性」に軸足を置いている点で、極めて成熟したAI観であるといえるでしょう。

