「日本の研究力を問う」神野直彦(東京大学名誉教授) マイあさ!(NHK) を聞いて
2025年9月29日に放送されたラジオ番組 マイあさ! マイ!Biz 「日本の研究力を問う」神野直彦(東京大学名誉教授)を聞きました。
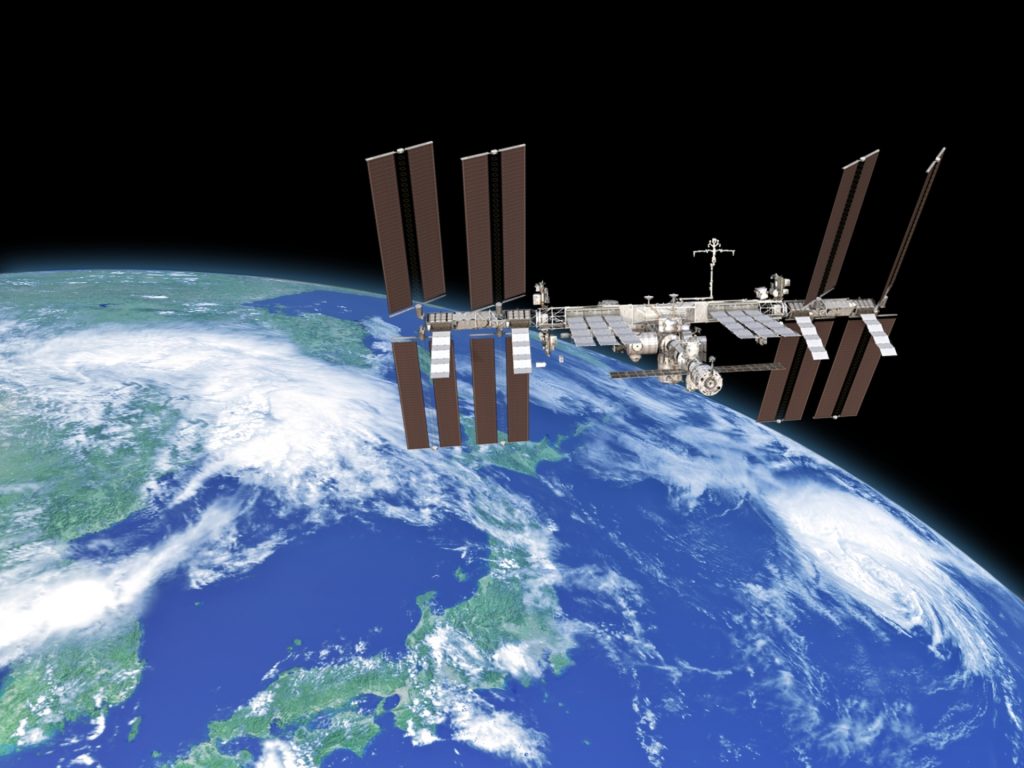
1.日本の大学ランキング低下と経済力の連動
番組は、日本の大学の国際ランキング低下を単なる教育問題ではなく、経済力の衰退と並行する社会構造的現象として描いています。
2004年には東京大学が世界12位に位置していたのが、2025年には28位に低下。
これは、単なる教育政策の問題ではなく、国家全体の研究・開発投資の縮小と、知の基盤の弱体化を象徴しています。
興味深いのは、「一人当たりGDPの順位低下」と大学の国際評価の連動に注目している点です。
研究力は経済の先行指標とも言え、「学問の衰退が国力の衰退に先立つ」という暗黙の警鐘が響きます。
2. 法人化以降の大学運営の変質
2004年の国立大学法人化を転換点として、大学が「経営的合理性」と「評価指標」に縛られていく過程が描かれています。
大学の研究時間が2002年の50.7%から2018年には40.1%に減少。
これは、研究そのものよりも書類作成や評価対応に時間が取られていることを示し、「評価のための評価」という自己目的化を生んでいます。
つまり、大学が「社会のための知を創る場」から、「自己の存続を守る組織」に変質してしまった危険性が指摘されています。
3. 研究資金とテーマの「選択と集中」
政府が研究資金を「稼げる分野」や「成果の出やすい分野」に集中投入する戦略を採っている点は、企業経営的な発想です。
短期的なROI(投資対効果)は見込みやすいが、基礎研究や哲学・文学といった長期的知的土壌が軽視されてしまう。
この部分で番組は、「研究分野を狭めると深まる」という発想の誤りを鋭く突いており、むしろ「研究を広く開くことでこそ、思いがけない深まりが生まれる」という逆説的な洞察を提示しています。
この視点は、まさに現代科学の「セレンディピティ(偶然の発見)」の本質を突いています。
4. 北欧モデルとの対比と提案
北欧諸国では、大学研究者と企業技術者が共同作業を行う「中間的な独立研究機関」が設立されており、番組ではそのような制度を日本でも導入すべきだと提案しています。
この構想は単なる批判ではなく、建設的な代替案を伴う点で非常に意義深い。
知の交流を制度化することで、大学は真理探究の自由を保ちつつ、企業は現場の課題解決に貢献できる「知の循環モデル」が描かれています。

5. 感想
聴いていて一番印象的だったのは、「大学は稼ぐためにあるのではなく、真理を探究するためにある」というシンプルなメッセージです 。
短期的な成果やランキングにとらわれず、長い時間軸で人類の知を積み上げていく姿こそ大学の本質。
その原点が揺らいでいる現状に危機感を抱くと同時に、北欧のような柔軟で共同的な仕組みに未来の可能性を感じました。
同時に、大学と経済がリンクしていることを改めて突きつけられ、「日本の研究力を回復させるには、社会全体の投資姿勢を変えなければならない」と痛感しました。
大学の問題は大学の中だけで解決できるものではなく、社会の価値観や優先順位を映す鏡でもあるんだな、と感じました。

