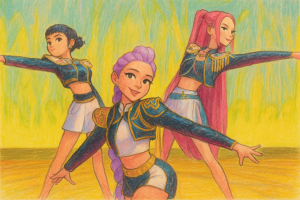マイあさ! マイ!Biz「“心理的安全性”の必要性」(NHK) を聞いて
2025年9月17日に放送されたラジオ番組 マイあさ! マイ!Biz「“心理的安全性”の必要性」を聞きました。
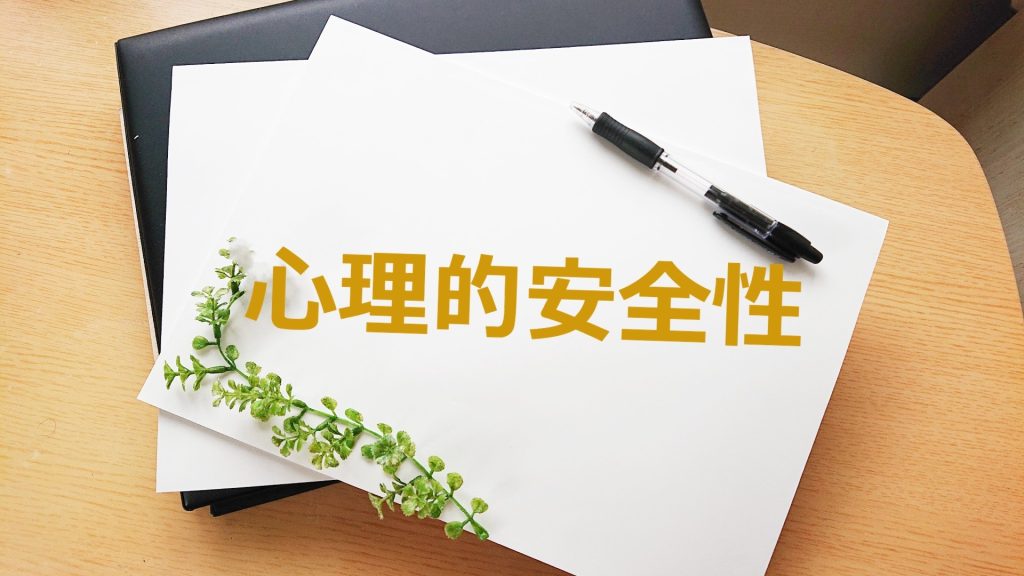
1.心理的安全性とは何か — Googleの発見
この番組は、心理的安全性を「ありのままの自分でいられることが周囲に認められている状態」と定義します。
重要なのは「拒絶されたり罰を受けたりしない」という安心感が共有されていること。
Googleの大規模な調査プロジェクト(2012年〜約4年間)により、「創造的な生産性」が高いチームに共通していた要素が、まさにこの心理的安全性だったという紹介は説得力があります。
技術系大企業が定量的に証明した概念を入り口にしており、リスナーに納得感を与える導入。
流行語ではなく「科学された信頼感」である点を明示している。
2. 優しさ=甘さではない:飛躍を支える厳しさ
番組では「優しくすること」が目的ではなく、「失敗しても大丈夫だから飛べ」と背中を押すことが真の心理的安全性だと語られます。
これは「温室育ち」の保護とはまったく異なります。ギリギリ達成できるチャレンジ目標を設定し、それを超える過程でこそ能力が最大限に引き出されるのです。
「安全」=「甘やかし」ではなく、「安全」だからこそ挑戦できるという逆説的な定義にハッとさせられました。
単なるぬるま湯文化と一線を画す洞察が秀逸です。
3. 組織文化のたとえ:カレーライス型 vs アイスクリーム型
カレーライス型:普段からスパイス(厳しさ)が効いているが、全体として温かみがある
アイスクリーム型:表面上は甘いが、冷たさ(無関心、拒絶)が本質
この比喩は非常に優れており、抽象的な組織風土の違いを、味覚と温度で直感的に理解させます。
この比喩は教育現場、家庭、企業すべてに応用可能。視聴者が自分の職場やコミュニティを内省するきっかけになります。

4. 「対話」こそが心理的安全性の鍵
心理的安全性の前提として、「日常的な対話(雑談)」と「リーダーの自己開示」が重視されます。
特に「個人面談=対話ではない」という指摘は鋭く、上意下達の関係性ではなく、フラットで相互的なやりとりが重要であるとされます。
コーヒータイム、3時のおやつといった小さな交流時間が、信頼関係構築の基礎になる。
「お子様組織」から「成熟した組織」へと成長させる鍵が、雑談と本音の共有である。
「心理的安全性のない会社には、これからは人が集まらない」という一言が非常に刺さりました。Z世代・ミレニアル世代の価値観にも合致しています。
5. 感想
この放送は「心理的安全性」を表面的な“やさしさ”ではなく、挑戦と失敗を可能にする土壌として描いている点が素晴らしいです。
特に「厳しくても最後は温かい」カレーライス型文化の提示は、単なる理論でなく日常生活に馴染む比喩によって理解を深める工夫がありました。
また、雑談やお茶の時間のような小さな習慣が、実は大きな組織文化を支えているという逆説的な指摘も光ります。
これは多くの日本企業が「制度改革」ばかりに目を向ける中で、“人と人の距離感”という根源的な要素を強調している点で、非常に価値があります。
特に印象に残ったのは、「優しさではなく安全性」という言葉です。組織における本当の安全性は、“失敗しても生き残れる”環境であり、それがあるからこそ人は思い切り挑戦できる。この視点は、学校や地域コミュニティなど、企業以外の場面にも広く応用できると感じました。
また、リーダーが弱さを見せられることの大切さも強調されていました。リーダーが「助けてほしい」と言えることは、むしろ組織全体の成熟を促す。
これは、協会や地域活動など、ユーザーご自身が関わる場面でも共感できるポイントかもしれません。
総じて、この放送は“心理的安全性”を単なる流行語でなく、人が生き生きと働き、挑戦し、失敗を経て成長するための普遍的な条件として鮮やかに示していたといえます。