「マイあさ!」 著者からの手紙「私たちはなぜ法に従うのか 法と「正しさ」をめぐる3000年の世界史」(NHK) を聞いて
2025年9月14日に放送されたラジオ番組 「マイあさ!」 著者からの手紙「私たちはなぜ法に従うのか 法と「正しさ」をめぐる3000年の世界史」を聞きました。

「法」への信頼の源泉への疑問
冒頭の「みんなは法を信じすぎている」という一文は挑発的であり、聴く者に強烈な問いを突きつけます。
この問題提起は、法が「正義」や「道徳」とは限らず、しばしば権威や制度によって正当化されてきた歴史があることを示唆しています。
古代ローマ:儀式と共同体の世界観
古代ローマでは、法は「市民法(jus civile)」や「慣習」に基づいており、そこでは宗教的儀式や神への祈りが不可欠でした。
このような法秩序は、共通の神話や宗教観を共有する閉じた共同体にしか機能しなかった点が指摘されています。ここから、法とは社会的前提に支えられた「信仰体系」でもあったという含意が導かれます。
商業と合理性による拡張
やがて商業の拡大により、法は宗教的な枠を超え、異なる文化背景を持つ人々の間での「約束事」としての性格を強めていきます。
合理性と手続きの透明性が求められ、「法」が普遍性を持つ仕組みへと変貌していく過程が明快に描かれています。
中世のカノン法:信仰と理性の架橋
中世ヨーロッパでは、カトリック教会によるカノン法が登場します。宗教的規範でありながら、そこには「理性的」「合理的」な法解釈も含まれており、信仰と理性の接点が見出されます。これは、後の法理学や人権思想の胎動を感じさせる重要なステップです。
近代の法思想とデカルトの転回
16〜17世紀、宗教改革や三十年戦争によって「神」「皇帝」「教会」といった伝統的な権威が崩壊し、絶対王政が登場します。
このとき、法は「支配者の命令」へと還元され、「外部の正しさ」に依拠しない法秩序が模索され始めます。
とりわけ、デカルトの登場は画期的です。彼は「外の正しさ」を信じず、人間の理性の中から正しさ(ルール)を導こうとしました。
「我思う、ゆえに我あり」という主観的確実性から、論理的に法の根拠を組み立てようとする試みは、現代の法哲学(自然法、契約論、立憲主義)につながる大きな転換点でした。
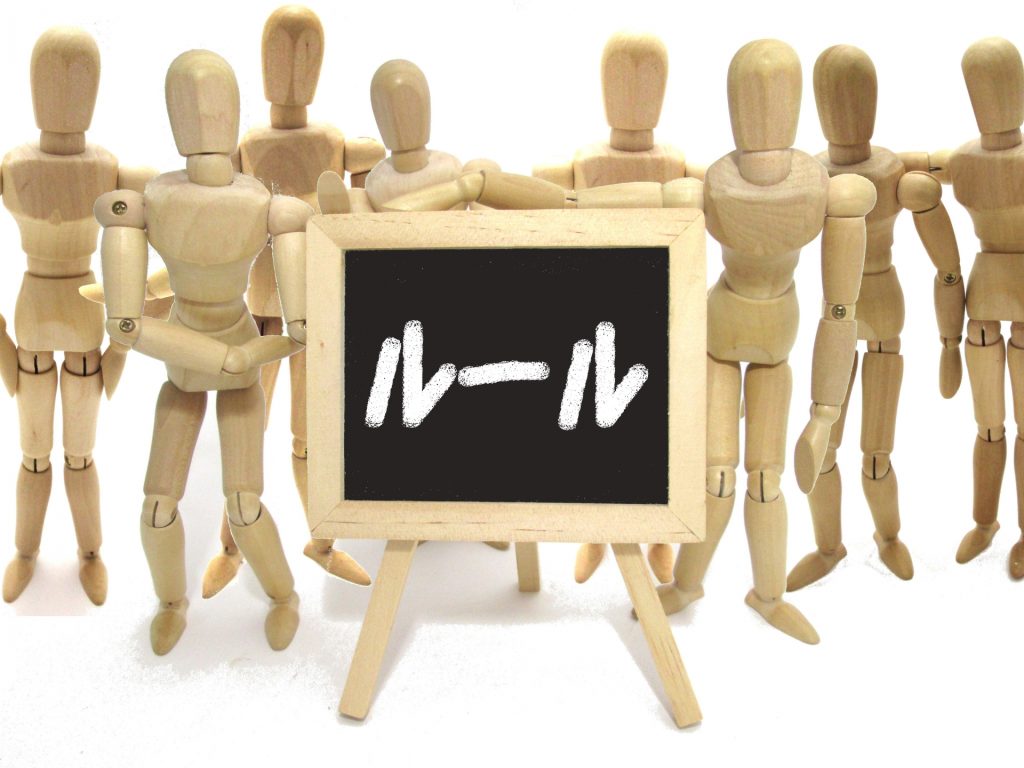
法と正しさの「検証」の姿勢
番組後半で語られた、「法は本当に正しいのか?」「我々の幸福に寄与しているのか?」という問いは、現代社会においてきわめて重要です。
形式的に整った法律であっても、その背後にある価値観や影響を批判的に問い直す必要があるという姿勢は、民主主義社会の根幹をなす「正義の検証作業」と言えるでしょう。
感想
本稿で紹介された内容は、単なる法制度の歴史を超えて、「正しさ」そのものの変遷と、それを制度化してきた人類の営みを描いており、非常に知的刺激に富んでいます。
聴きながら、「私たちは法を“信じている”のか、それとも“検証している”のか」という根源的な問いを突きつけられた感覚を持ちました。
特に印象的だったのは、「法の正しさは疑われなければならない」という部分です。法が絶対であると思い込むことは危険であり、むしろ私たち市民一人ひとりが、その内容や運用を常に批判的に見ていくことこそ、民主的法秩序を支える礎だというメッセージは、現代社会への重要な示唆を与えています。
高校生にも理解できるように噛み砕かれつつも、本質的な問いを提示するこのラジオ解説は、市民教育・法教育の教材としても非常に有用です。
法の歴史を哲学・宗教・政治と交差させて説明する構成は、単線的でない「立体的理解」を促します。
このラジオ放送は、「法=正しいもの」という無意識の前提をほぐし、人間が自らつくった制度を、自らの理性で支え直す努力の大切さを説いています。
現代社会において、法が果たす役割の根本を見つめ直す機会として、深い洞察と価値を提供してくれる素晴らしい内容でした。
