「フランスの書店事情」向井麻里(ヨーロッパ総局記者) ラジオ番組「マイあさ!」(NHK) を聞いて
2025年9月9日に放送されたラジオ番組 マイあさ! 「フランスの書店事情」向井麻里(ヨーロッパ総局 記者)を聞きました。
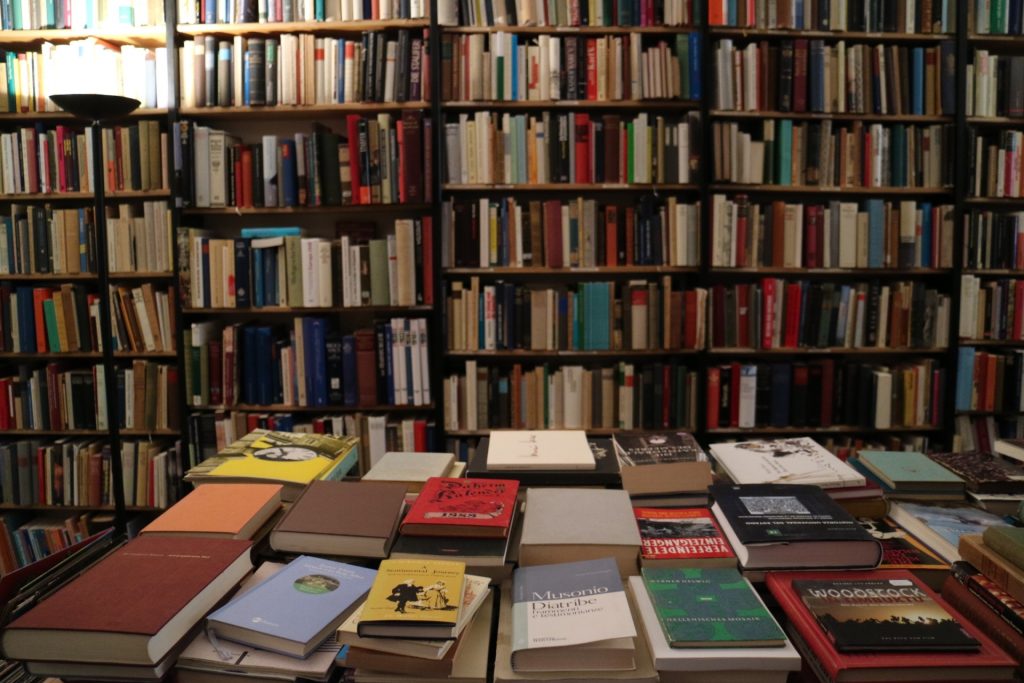
1.書店を守るための法制度:「反アマゾン法」と価格統制
フランスでは2014年に制定された「反アマゾン法」によって、オンライン書店による無料配送の禁止と書籍の価格維持(5%以上の値引き禁止)が行われています。
これは一見「消費者の不利益」に見えるかもしれませんが、本質は書店という文化資源の保護です。
この価格統制により、巨大資本のダンピングに押されることなく、中小の独立系書店が生き残れる土壌が確保されている点は非常に特徴的です。
日本でも長く再販制度がありますが、それに加えて配送まで制限するという姿勢は、「本をモノではなく文化として扱う」思想の現れです。
2. 若者に文化を届ける革新的制度:「カルチャーパス」
2021年から導入されたカルチャーパス(Pass Culture)は、若者に文化体験の機会を与える施策として注目に値します。
アプリを通じて書籍購入や映画・演劇などに使える金額が支給され、18歳では300ユーロ(後に150ユーロ)という金額が支給されました。
この制度の効果として、「若者の読書量が増えた」という政府発表は、教育や文化振興の観点から極めて意義深いものです。
日本でも「読書離れ」や「若者の文化消費の減退」が課題となっている中で、文化を支援する国家の明確な意思が表れた制度です。
3. 書店の自助努力と文化的進化
制度的な保護だけでなく、書店側の創意工夫も印象的です。
店内にカフェ併設、
可動式の本棚でイベントスペースを創出、
書店員による手書きのポップで「本との出会い」を演出
これらは、書店が単なる「販売の場」から「体験と出会いの場」へと進化していることを意味します。
書店が「街の文化装置」として再定義されている姿には学ぶところが多いです。
4. 人材育成という未来投資:「書店の学校」
書店員を育てる「書店の学校」まで存在するという点には驚かされます。
本を売るのではなく、本との出会いを支える人を育てるという文化的ビジョンが背景にあります。
日本であれば図書館司書や書店員の研修制度はあるものの、「文化担い手」としての職業教育という視点はまだ発展途上です。

5. 感想
フランスの取り組みからは、「文化を守る」という受け身の姿勢ではなく、「文化を育て、届ける」という能動的な国家戦略が感じられます。
それは制度・経済・教育・生活の各層に貫かれており、「文化立国」の姿勢を体現しています。
書店が単なる小売業ではなく、人と本、人と文化をつなぐハブとして再定義されている姿には感動を覚えます。
日本でも地元に根ざした書店が奮闘していますが、制度的支援との連携がまだ弱いのが現状です。
フランスの事例は、書店を通して地域文化と民主主義を支える仕組みの可能性を示しています。
カルチャーパスのように、「若者の文化的可処分所得」を国家が補填するという発想は斬新で、民主主義と文化の持続可能性にとって重要です。
読みたい本に出会い、観たい映画に触れられる機会が、家庭の経済力に左右されない社会。これは格差是正と文化政策の融合モデルと言えるでしょう。
本と人の出会いを、どう守り、育てていくか。
この問いに対するフランスの一つの答えが、制度、現場、若者支援という多層的な取り組みで示された番組内容でした。
書店の未来は、文化の未来であり、民主主義の未来でもある——そう感じさせられる、知的刺激に満ちた内容でした。

