「デフレに陥る中国」津上俊哉(国際問題研究所) ラジオ番組「マイあさ! 」経済のイマ (NHK) を聞いて
2025年9月8日に放送されたラジオ番組 マイあさ! Biz 経済のイマ 「デフレに陥る中国」津上俊哉(国際問題研究所) を聞きました。
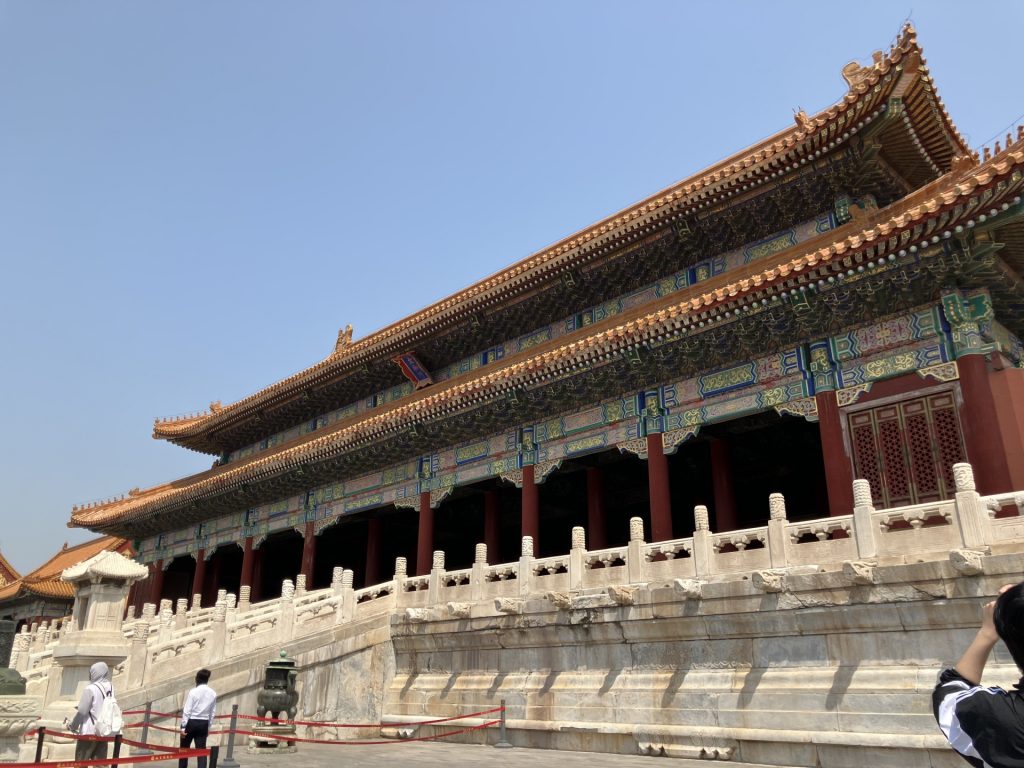
1.「名目」と「実質」の乖離が示す深刻なデフレ傾向
番組はまず、中国のGDP成長率に注目し、実質成長率5.4%に対して名目成長率が4.6%と下回っている点を取り上げています。
この差異は、物価が下がっている=デフレ的な圧力が高まっている証左です。
かつての日本も、2000年代に名目成長率が実質成長率を下回る「名実逆転」の状況が10年にわたり続きました。
これと酷似する現象が中国で始まりつつあるという点は、先進国型の「成熟経済」における共通の陥穽を示しているとも言えます。
2. 不動産バブル崩壊と地方政府の財政圧力
番組では、中国の地方政府が自らの財政を維持するために、地元企業に過剰な売上ノルマ(=税収目標)を課し、それが採算無視の値下げ競争を招いている構図を鋭く指摘しています。
この構造は、「企業と地方政府の共依存関係」という、中国独特の発展モデルの歪みが露呈した事例と言えるでしょう。
値下げが価格競争を生み、結果として需要の停滞・収益悪化→さらに値下げという負のスパイラルが進んでいます。
3. デフレの負の連鎖と構造的な信用収縮
家計と地方政府の高水準の債務が、デフレによって実質負担を増大させ、消費・投資行動を萎縮させるメカニズムが丁寧に解説されていました。
これにより、以下の3重苦が生じていることが浮き彫りになります。つまり、返済負担の増加、将来不安による消費の先送り、投資意欲の減退です。
このような状況下では、「金融緩和だけでは不十分である」という指摘は極めて本質的です。
実体経済側の再構築(バブルの後処理、負債圧縮など)こそが真の処方箋であるとの視座は、きわめて説得力があります。
4. 公共料金値上げのジレンマと生活コストの逆風
番組後半では、北京・上海などで地下鉄や水道料金の値上げが予想されることに触れ、それが生活者に与える打撃と、さらなる消費の減退を予兆しています。
これは典型的な「スタグフレーション的現象」への懸念とも読めます。
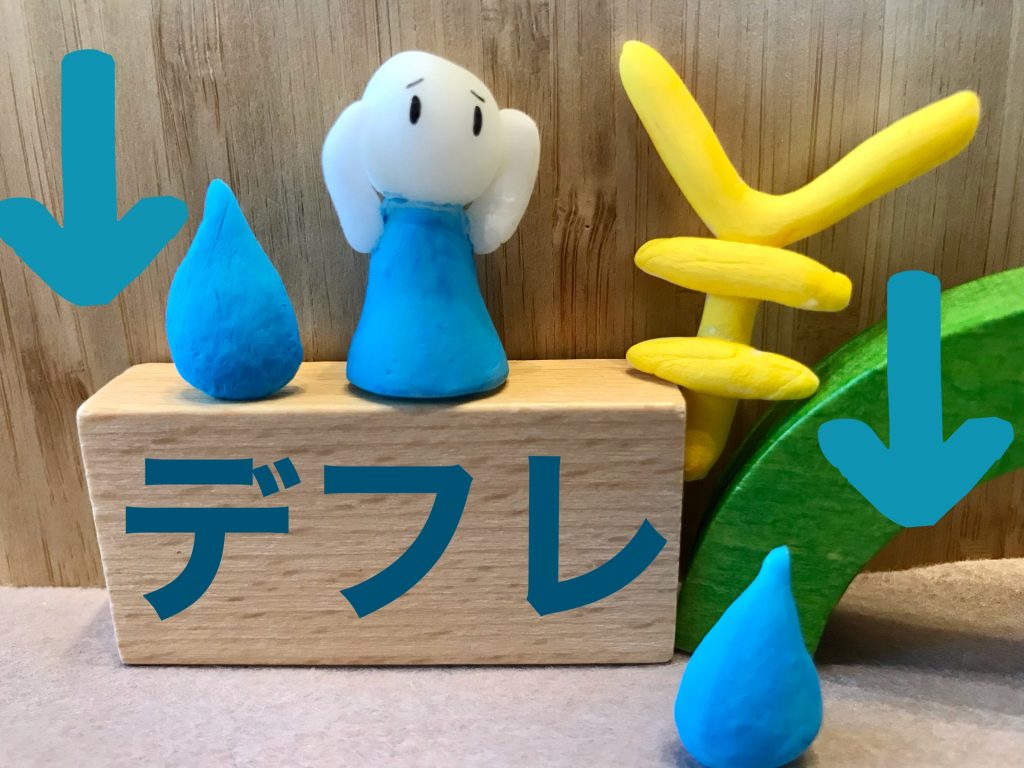
5. 中国政府の対応:表層的な緩和策の限界
「物価の合理的水準の維持に努める」といった表現は、実態に対する距離感が感じられ、リスクの本質にまだ踏み込めていない印象を受けました。
日本の失敗の轍を踏まぬためにも、中国は今、決断の時を迎えているのではないでしょうか。
6. 感想
本放送は、中国経済の実情を「数字」「制度」「生活者」の各視点から立体的に描き出しており、その構造的問題点を、日本の経験と重ね合わせることで、聴き手に強い説得力と警鐘を与える内容でした。
特に印象深かったのは、地方政府と企業の関係性が招く価格競争の病理です。それは単なる市場原理では説明できない、制度設計そのものが引き起こすデフレ圧力であり、このような「構造の歪み」こそが、経済を蝕む本丸だというメッセージは鋭いものがあります。
中国のデフレ問題は、単なる経済的現象にとどまらず、「社会モデルの岐路」に立たされている証拠です。
中国がどう行動するのかは、グローバル経済全体にも大きな影響を与えるでしょう。
そして日本自身も、「過去の教訓を他者の鏡として生かせるか」が問われているように感じます。
デフレの渦中にあった時代を乗り越えた今だからこそ、日本の視点が貢献できる知見もあるのではないか。
そんな前向きな問いかけを与えてくれる放送でした。

