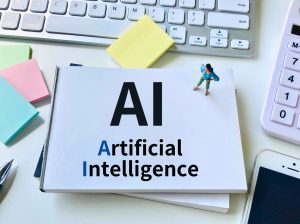マイあさ! 「日本の造船業 デジタル化でどう変わるか」(NHK) を聞いて
2025年8月18日に放送されたラジオ番組 マイあさ! 「日本の造船業 デジタル化でどう変わるか」を聞きました。

番組はまず、日本の造船業がかつて世界の5割を担っていた事実を強調し、現在は中国・韓国に押されて15%にまで低下した現状を示しました。
この数字は、日本が技術力を誇りながらも「国策支援の不足」「事業規模の小ささ」「非効率な慣習」といった構造的問題を抱えていることを示しています。
特に中国や韓国は政府主導での再編・統合を進め、スケールメリットを武器に国際競争力を高めたのに対し、日本は事業者ごとの分断や独自のやり方に固執している点が浮き彫りになっています。
造船業の特徴として、一隻ごとにオーダーメイドで大量の部品(1000万件以上)を扱い、複雑な工程を要することが強調されました。
ここで問題となるのが、設計と製造の断絶です。
設計側は3D CADを活用しているのに、現場は「紙の図面」しか受け付けない。
その結果、デジタルデータが無駄に紙に落とされ、工程間で情報が途切れる。
つまり、単なるIT導入ではなく「現場の意識改革」と「部門間の標準化」が不可欠だと論じられています。
これは、単なる技術課題ではなく、組織文化や慣習の問題であることを浮き彫りにしています。
具体的な改革について、番組では、いくつかの成功例が紹介されました。
データ標準化と共通化により、工程ごとのコストや売上をリアルタイムで可視化した会社。
データサイエンティストの社内育成により、法律や経営を専門とする社員までがプログラミングを駆使し、分析に参加できる体制を整えた会社。
RFID(電波を用いてタグのデータを非接触で読み書きするシステム)をヘルメットに搭載して、作業員の動きを「見える化」した会社。
これらは「現場DX」の実践例であり、利益を従業員に還元することでモチベーションを高め、改革が持続する好循環を作り出している点が注目されます。
造船業という一般に馴染みが薄い分野を、具体的な数値や現場の習慣に踏み込んで説明しており、理解しやすい構成でした。
また、単に「IT化すればよい」と抽象的に語るのではなく、「なぜ紙に戻してしまうのか」といった現場固有の障壁を指摘した点は説得力があります。
この番組を聞いて強く感じたのは、日本の造船業が「技術力では劣っていないのに、組織文化と情報共有の非効率さで競争力を削がれている」という現実です。
いわば「宝の持ち腐れ」の状態に陥っているわけです。

番組が強調した「現場に根ざしたキーマン」「横串の視点」は、造船DXの要諦を突いています。
“現場の知恵”を消さずに“全体最適の仕組み”に昇華する、その媒介がデジタルです。
ただ、現場の知恵と柔軟な対応力は日本の造船の強みであり、これを完全に標準化で押しつぶすのではなく、デジタルと現場力の融合こそが生き残りの道ではないかと思います。
つまり、「一律の効率化」ではなく、「現場の工夫を生かしつつ、データで裏打ちされた柔軟な対応力」を磨く方向性が理想でしょう。
番組の最後に語られていた「造船には誇りを持って働く人が多い」という言葉は印象的でした。
技術大国としての誇りを未来につなぐには、デジタル化を「人を置き換えるもの」ではなく「人の力を引き出す道具」と位置づけることが重要だと感じました。