「日銀の株保有を考える」水野和夫(経済学者) ラジオ番組「マイあさ! 」経済展望(NHK)を聞いて
2025年8月8日に放送されたラジオ番組 マイあさ! 経済展望「日銀の株保有を考える」水野和夫(経済学者)を聞きました。

この放送内容を整理しつつ、さらに掘り下げて分析すると、論点は大きく3つに分けられます。
① 日銀ETF保有の背景と異例性
(A) 導入経緯
2013年の「異次元緩和」期に、デフレ脱却と円高阻止のため、国債購入で金利を下げつつ、ETF購入によって株価下支えを行った。
株価は当時1万2千円程度で「割安」と判断された。
(B) 世界的な異例性
アメリカや欧州では中央銀行による株式保有は禁止されており、日本は先進国で唯一のケース。
(C) リスクの本質
国債は満期保有で元本保証があるが、株式は価格変動リスクを伴い、損失が出れば日銀券(円)の信認低下につながる可能性がある。
つまり、中央銀行が事実上の「株式投資家」になるという構造的なリスクを抱える。
(D) 分析ポイント
ETF購入は短期的には市場安定策として有効だったかもしれませんが、本来の中央銀行のミッション(通貨・物価の安定)と株価安定の目的が混ざり、政策領域が拡散しています。
これは「中央銀行の役割逸脱」問題であり、金融政策の透明性や独立性を損なう危険があります。
② 現状と課題
(A) 国債減額は進行中:2024年2月の国債保有600兆円が、2025年6月には567.5兆円まで減少。
ETFは横ばい:依然として37兆円超を保有し、売却は後回し。
(B) 売却を遅らせる理由:株価下落リスクを懸念。不況局面での売却は市場を悪化させる恐れがある。
(C) 分析ポイント
ETFの売却が進まない最大の理由は「市場ショックの回避」。
しかし、保有残高が大きすぎるため、売却タイミングを逃し続ければ「永遠に売れない資産」化し、将来の市場混乱リスクを先送りするだけになります。
特に、株価が高いときに売らなければ元本割れリスクは高まります。
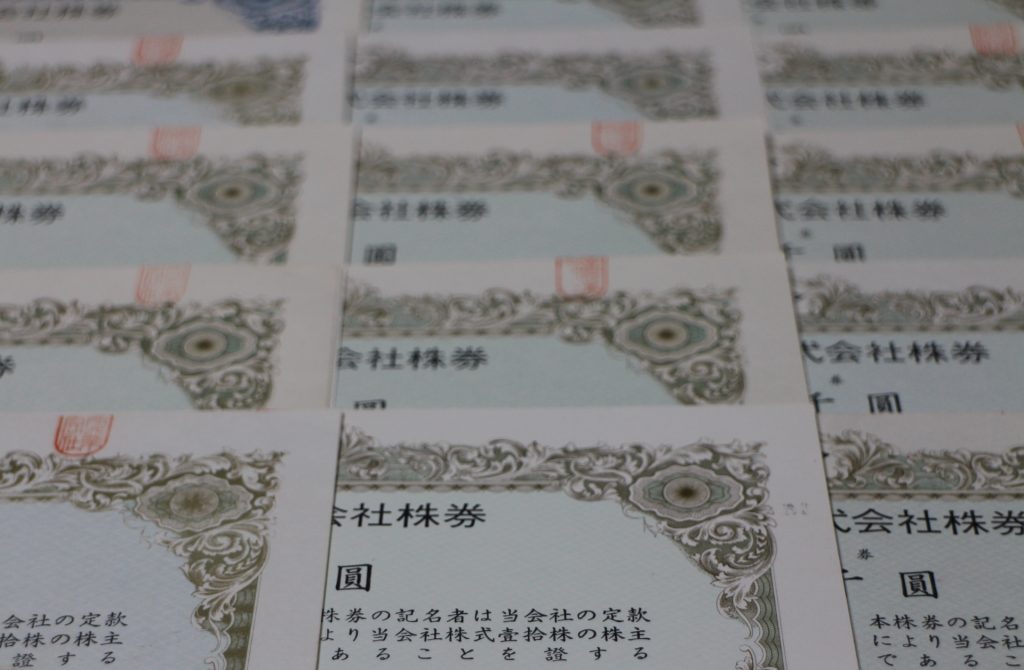
③ 提案されている出口戦略
(A) 年間売却額(例:5兆円)を事前公表し、市場の予見可能性を高める。
(B) 東証時価総額1013兆円に対して0.5%程度の売却は吸収可能。
(C) 不況期には売却中止など柔軟な条件設定。
(D) 分析ポイント
出口戦略の鍵は「市場予見性」と「緩やかな実行」。予告型・定量型の売却は確かに混乱を和らげますが、実際には投資家が先回りしてポジション調整するため、発表時点で株価に影響する可能性もあります。
また、売却益や損失の処理をどう日銀のバランスシートに反映するかも議論が必要です。
感想
この問題は、短期的な景気下支えと長期的な金融の健全性が正面衝突しているケースです。
ETF保有は「デフレからの緊急脱出」という非常手段でしたが、10年以上経っても出口が見えないのは、当初想定以上に副作用が大きい証拠でしょう。
以上のように、ETFプログラムは副作用もかなりありましたが、デフレ心理の転換局面で“橋”として機能したのも事実です。
橋を渡り終えた今は、市場機能を尊重しつつ、時間を味方につけて静かに橋を撤去する段階――そう受け止めました。

