マイあさ! マイ!Biz 「時短AI活用術」を聞いて
2025年8月6日に放送されたラジオ番組 マイあさ! マイ!Biz 「時短AI活用術」を聞きました。
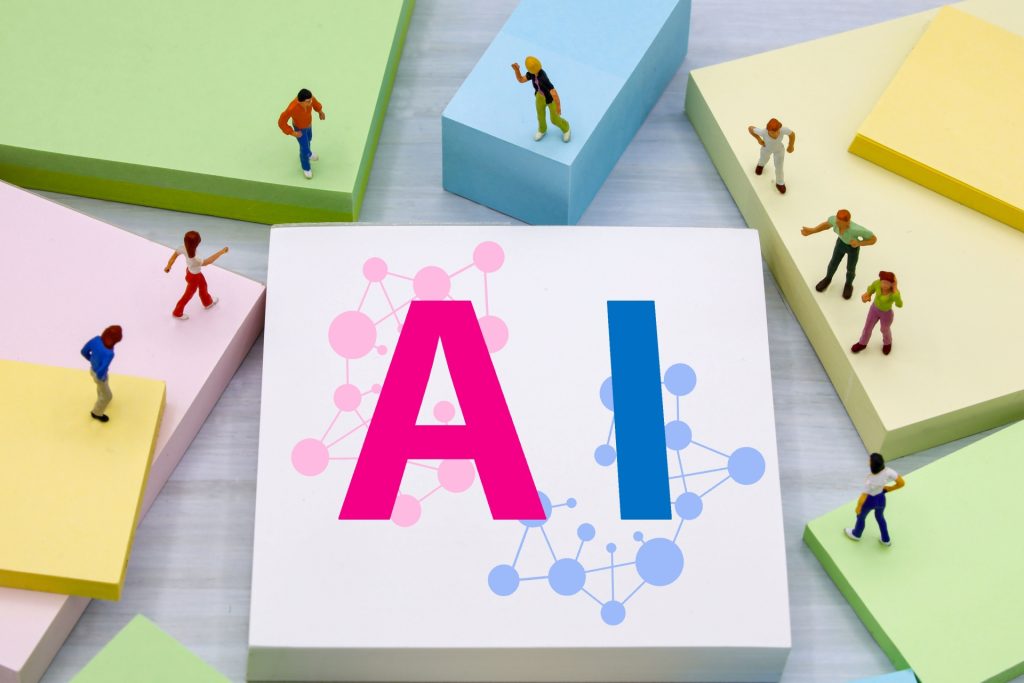
- 生成AIの壁打ち的活用
冒頭で紹介されたのは、生成AIを“壁打ち相手”のように使う方法です。
つまり、企画のアイデアをAIに投げかけ、フィードバックや視点の補完を受ける形で、自分の思考を整理・発展させるという使い方です。
これは特に、初期アイデア段階やブレインストーミングにおいて人間の発想の幅を広げる効果があります。
AIを“答えを出す道具”としてではなく、“考えを深める補助線”として活用する発想の転換が大事である。 - マルチモーダルとAIエージェントの進化
従来はテキスト入力が主な指示方法だったが、現在では「マルチモーダル」(テキスト+画像+音声+ファイルなど)の技術により、複数のデータ形式を一括で処理できるAIが登場。
さらには、目的を持って自律的に行動する「AIエージェント」の登場により、資料作成などを“ほぼお任せ”できるフェーズに入ってきている。
従来の「道具としてのAI」から、「アシスタント型エージェント」への進化しつつある。今後の業務プロセス全体を再設計する鍵になる可能性がある。 - 具体例:プレゼン資料の作成支援
「ジェンスパーク」というAIエージェントを活用し、議事録や目的に応じたプレゼン資料を自動で生成する事例が紹介されています。
取引先向けか社内向けか、という目的に応じた「文脈理解力」がAIに求められており、それに対応できるようになっている点は驚異的です。
AIによる“文脈に応じたアウトプット”が実用レベルに到達している。 - ゆるプログラム=非エンジニアでも自動化
「ゆるプログラム」という言葉で紹介されたのは、ノーコードでの自動化支援です。
AIが簡単な業務アプリ(例:ファイル整理プログラムなど)を日本語だけで構築できるという内容です。
ここでは、“素人でも業務効率化ができる”という民主化の側面が強調されていました。AIがエンジニアの役割を部分的に担い始めている。 - 課題:使い方の習熟とリスク管理
便利である一方、AIへの指示の出し方にはコツが必要であり、初心者には一定のハードルがあります。
また、機密情報をクラウドにアップするリスクや、AIに頼りすぎて人間の判断をおろそかにする危険性にも触れられています。
“万能”ではなく、“使いこなすためのリテラシー”が前提条件になっている。
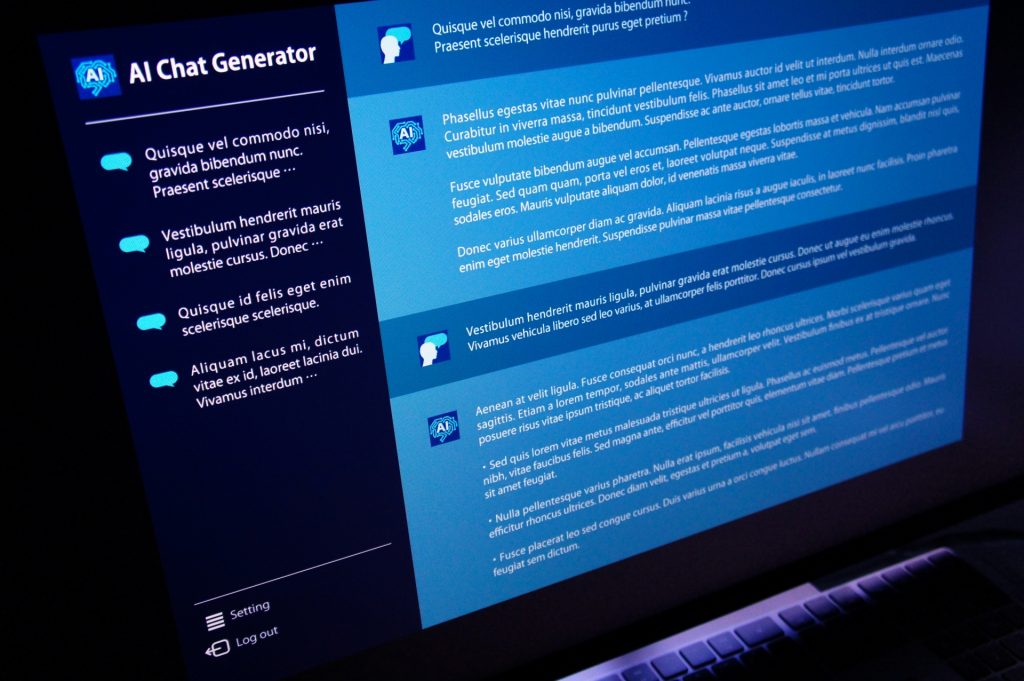
感想
この番組を通じて、「生成AIはもはや時短ツールとして実用段階に入っている」ことが明確に伝わってきました。
とりわけ印象的だったのは、AIが単に作業を代行するのではなく、“人間の思考を助け、文脈を理解し、適切な形にまとめてくれる”存在になりつつあるという点です。
ただし、万能ではありません。
むしろ、「AIの得意なことはAIに任せ、人間は人間にしかできない判断や創造に注力する」という作業分担のバランス感覚が今後ますます大切になると感じました。
また、「具体的に指示する力」「どこまで任せるかを判断する力」など、AI時代に求められる新しいスキルセットにも目を向ける必要があります。
