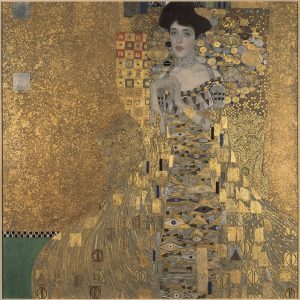「ラジオ深夜便 旅の達人 温泉について」を聞いて
2025年7月6日に放送された「ラジオ深夜便 旅の達人 温泉について」を聞きました。

この番組は、単に温泉の紹介にとどまらず、「温泉文化」の奥深さや、日本人の精神性、そして現代社会における温泉の新たな役割まで幅広く掘り下げていました。
山崎さんは、温泉を「癒し」や「観光資源」として楽しむだけでなく、学問として体系立て、産業として活用する視点を持っています。
温泉の歴史や泉質、分析表の読み方などの基礎的な知識だけでなく、配信事業など新しい観光ビジネスにも目を向けていることが印象的です。
これは、温泉を「地域資源」としてどう活かすかという現代的な課題意識でもあります。
栃尾又温泉で語られた「ぬる湯に長く入って、体の凝りや心の執着が溶け出していく」感覚は、単なる温浴効果を超えた「精神的浄化」のようなものです。
温泉と自分が一体化するという表現には、まるで禅や瞑想のような「無になる」感覚が宿っています。
温泉が日本人にとって「癒し」や「浄化」の場であることを象徴するエピソードです。
海外の温泉は医療やリハビリとして扱われることが多いですが、日本では「温泉旅館」「温泉街」「女将」など、周囲の人や文化が温泉の魅力を形作っています。
ブダペストに住む日本人によって語られた「日本人が一番恋しくなるのは温泉」という話も、日本の温泉が単なる入浴以上の「心のふるさと」として機能していることを示しています。
バリアフリーの進展は、超高齢社会に対応する実用的な取り組みです。
一方、一人温泉の広がりは、コロナ禍や自分時間の充実志向といった背景から生まれた新しい楽しみ方です。
「自由に自分のペースで過ごす」「何度も好きなときにお風呂に入る」という一人旅ならではの贅沢さが、現代人の心に響いています。

那智勝浦の「洞窟風呂」、猪苗代の「沼尻温泉」など、温泉がただの建物の中にあるのではなく、自然そのものと一体になって存在していることが紹介されました。
海の波音や、酸性硫黄泉の強烈な泉質など、自然の厳しさや美しさをそのまま体験できる温泉の魅力です。
この番組を聞いて、温泉とは単なる「観光地」や「癒しの場」ではなく、日本人の暮らしや心に深く根付いた「文化」であることを再認識しました。
とりわけ、温泉に「身を浸す」のではなく「自分が温泉と一体になる」という表現に心を打たれました。
また、温泉を未来にどう残していくか、どう新しい価値を作るかという課題意識も感じられました。単なるノスタルジーではなく、次世代に向けた「温泉文化の進化」が求められているのだと思います。
一人温泉の楽しみ方も、現代人の「孤独を楽しむ」「自分と向き合う」という新しい旅のスタイルとして共感できます。
私も忙しい日々の中で、ふと「誰にも邪魔されず、静かに温泉に浸かってみたい」と感じました。