マイあさ! マイ!Biz「ファーウェイの戦略に見る米中ハイテク争いの行方」を聞いて
2025年7月2日に放送されたラジオ番組 マイあさ! マイ!Biz「ファーウェイの戦略に見る米中ハイテク争いの行方」(NHK)を聞きました。

ファーウェイは、米国の厳しい輸出規制を受け、自社のエコシステム構築を加速しています。
ファーウェイはスマホや通信機器企業という枠を超え、AIサーバー、スーパーAI、世界モデルなど、インフラから応用まで幅広いAI関連技術の開発を進めています。
AIは単なるツールではなく、国家の競争力そのものと考えていることがわかります。
米国技術が使えない部分を自前で補完し、スマートフォンから家電、車まで統一したOSで囲い込むことで、「ファーウェイ経済圏」=「脱アメリカ経済圏」を築こうとしています。
アメリカによる半導体規制は、中国の技術開発に大きな痛手です。
しかしファーウェイは、複数のチップを組み合わせ、計算能力を分散処理する設計、自国製の半導体や代替技術を駆使して、実用レベルの性能を確保、つまり、アメリカ製の最高性能チップに頼らなくても、「十分使えるもの」を作る方向にシフトしています。
ここには、完璧を求めるより、必要十分な性能と低コストのバランスを取る現実主義的な姿勢が見えます。
アメリカは、技術優位を守るために規制を強化していますが、中国も独自の道で進んでおり、「絶対的な勝者」はいないまま、双方が消耗戦に突入しているように感じます。
アメリカは、技術的優位を維持するが、中国市場を失うことになるし、中国は、短期的には遅れをとるが、内製化と技術独立を加速しています。
これはまさに、冷戦時代の「宇宙開発競争」に似た状況です。
両国とも妥協せず、互いに自国技術で覇権を取ろうとしています。
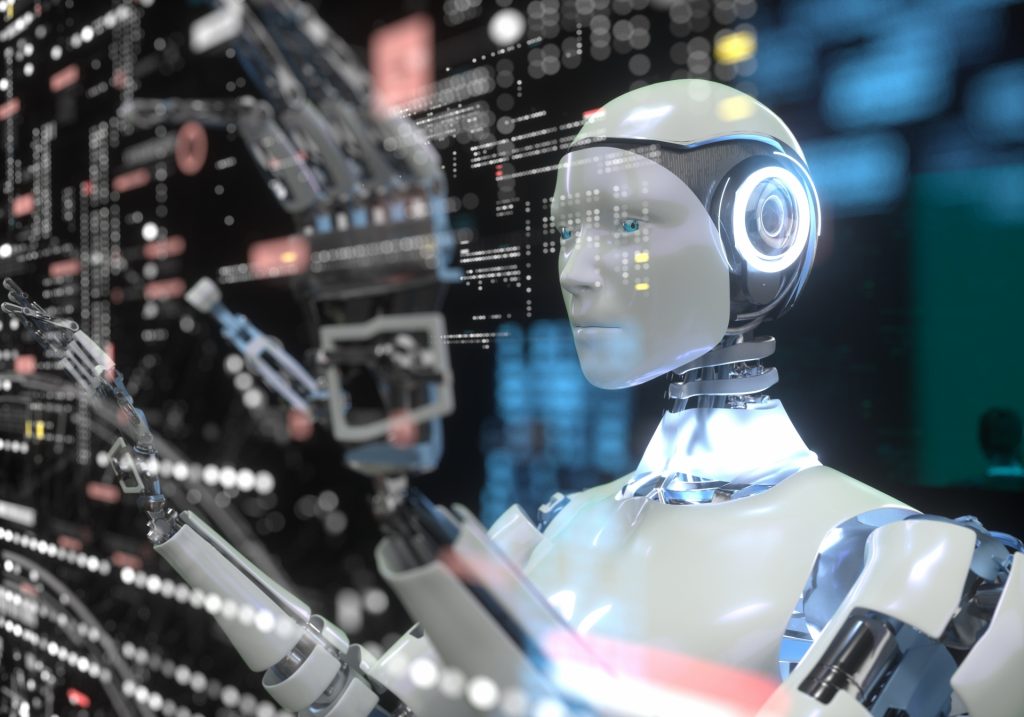
ファーウェイの存在は、発展途上国やコスト重視の国々にとって重要な「選択肢」を提供しています。
米国製品が高価で手が届かない国でも、ファーウェイ製品ならば実用レベルで使えるということです。
ただし、その裏には「中国の影響力拡大」という政治的リスクも含まれることになります。
単純に「技術力」だけでなく、地政学的な駆け引きとして世界がどちらの陣営につくかという問題も絡んでいます。
これから5年~10年、中国がどれだけ自立できるかが、世界経済のバランスに大きく影響するでしょう。

