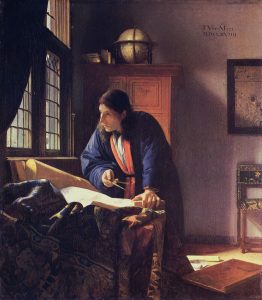美の巨人たち 黒田清輝作 「湖畔」を見て
今日の一枚。黒田清輝作「湖畔」

『描かれているのは、うちわを手に湖畔で涼をとる浴衣姿の美しい女性。
山の端に日がおちかけている高原の夕景です。
背景の遠くなだらかな山並みも、さざ波たつ湖面も、浴衣の色も、水色がかった淡い色彩で統一され、人物と風景が一つになって溶け込んでいます。
油彩画とは思えぬ清涼感溢れる画面。
女性の目元も涼やかです。
一見風景画のようで、それでいて肖像画のようでもあり、不思議な魅力を持ったこの一枚の絵が、日本の洋画に変革をもたらしたのです。
「女と水」の主題は西洋でも昔から描かれており、レオナル・ド・ダビンチのモナリザにもそれにあたります。
それをどのように日本の主題にしていくかっていうことが大きなテーマでした。
油絵具は、普通油を使ってるか不透明じゃないかと思うんですけど、実は非常に透明感があります。
原色に近い形で絵の具を使い、それを薄く薄く塗り重ねることで、淡い独特の色彩を実現したのです。
また、ちょうど浴衣の袖口のあたりに、キャンバス地がそのまま見えます。
よく見れば、山と湖面の境目にも塗り残しがあります。
そういうことによって、しとっとしていて湿度のある日本の風土よく表してる。
しかし、黒田は単に日本の風土を表現しただけではありません。
日本人は人間は自然の一部であると考えてきました。
それが日本人共通の美意識と言っていいかもしれません。
黒田がこの景色を目の当たりにして、絵に込めようとしたもの。
それは、日本人の自然観でした。
塗り残しによって、山や湖という自然のまるで一部であるかのように、人物が溶け込んでいるのです。
この湖畔で、日本における新しい油絵の可能性を見事に描き出しました。
西洋で学んだ水と女性というモチーフを、日本人の自然観で描くことで。』

番組を見て分かるように、この絵は、一見すると単なる「美しい女性と風景」の絵のようでありながら、実は西洋画法と日本の自然観が融合した、日本近代洋画史における画期的な一作です。
まず目を引くのは、画面全体に広がる涼やかで繊細な色彩です。
水色を基調とした浴衣、静かな湖面、遠く霞む山々――すべてが統一された淡いトーンで描かれ、まるで絵の中の空気そのものが肌に感じられるような、湿度や涼しさまでもが伝わってくるようです。
とくに、絵の具を何層にも薄く重ねることで得られたという透明感は、油絵であることを忘れさせます。
さらに、女性の視線や姿勢にも注目したいです。
直接こちらを見ず、静かに湖を眺める姿には内省的な美しさがあり、彼女の存在は「湖畔」という自然の中に溶け込むように描かれています。
キャンバス地の塗り残しすらも、その意図を強めています。
これは、単なる技術の痕跡ではなく、人間と自然が一続きであるという日本的な世界観の象徴です。
番組でも触れられているように、「女と水」というモチーフは西洋美術における伝統的なテーマですが、それを黒田清輝は、日本の風土と精神性に根ざした表現に変換したのです。
これは、単なる様式の模倣ではなく、西洋画法を取り入れつつも、日本独自の価値観を可視化した革新だといえます。